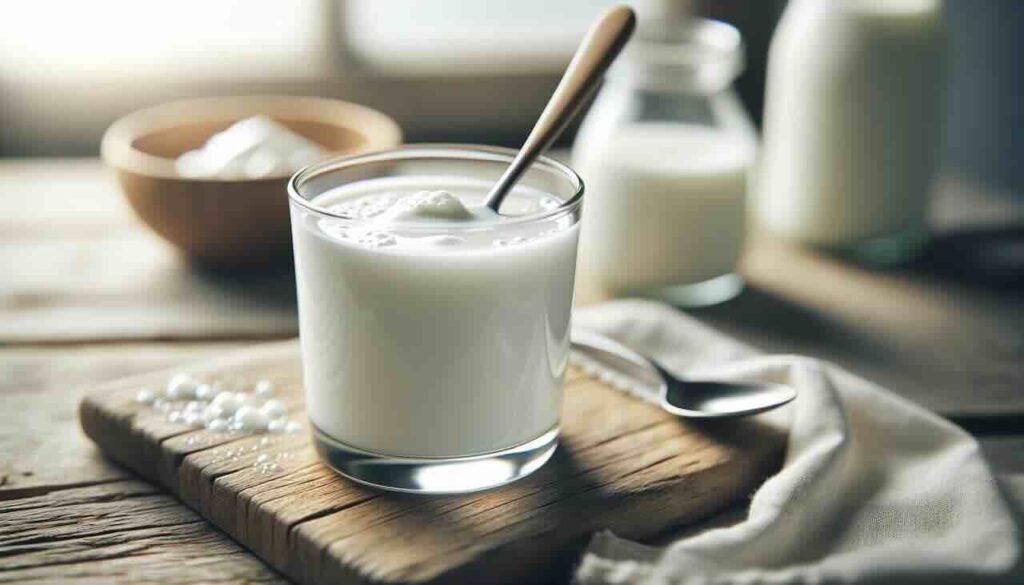夏になると食べたくなる、つるりと冷たい「ところてん」。でも「寒天と同じじゃないの?」「ゼリーと何が違うの?」と思ったことがある人も多いはず。実はところてんは、日本の食文化に根ざした独特の食品なんです。
この記事では、ところてんの由来や製法の違い、名前の由来などを詳しく紹介します。
結論:ところてんは奈良時代からある日本発祥の海藻食品
ところてんは、日本で古くから親しまれてきた、海藻を原料とした和の食べ物。奈良時代から食されており、現在もその製法は大きく変わっていません。寒天やゼリーとは原料や食感がまったく異なる別の食品です。
ところてんの原料と歴史
ところてんの主な原料は、天草(てんぐさ)という海藻の一種です。これを煮出して、濾して、冷やし固めることで完成します。
その歴史は奈良時代にまでさかのぼり、『本草和名』などの古文書にもその記録が見られます。江戸時代には庶民の間でも夏の涼味として人気となり、屋台で売られるなど、夏の風物詩として定着していきました。
寒天・葛切り・ゼリーとの違い
よく似た食べ物に見えても、ところてんと寒天・葛切り・ゼリーは全く別物です。
- 寒天との違い
- 寒天も天草が原料ですが、一度乾燥させたものを使います。
- 粘りや弾力が少なく、ところてんよりも硬く仕上がるのが特徴です。
- 葛切りとの違い
- 葛切りは葛粉から作られます。
- なめらかで柔らかい舌触りで、温・冷どちらでも食べられることが多いです。
- ゼリーとの違い
- ゼリーはゼラチンや寒天を使った洋菓子で、果汁や砂糖を加えて作る甘味。
- ところてんは無味で、タレや黒蜜をかけて食べます。
ちなみに、ところてんに黒蜜をかけるスタイルは関西や九州地方に多く見られます。
三色団子の色と順番の意味でも、和菓子の地域差が紹介されています。
名前の由来と「心太(ところてん)」の意味
ところてんの漢字表記「心太」は、当て字です。
- 「心」は「ところ」と読ませる古語読み。
- 「太」は「てん」と読ませる洒落的な当て字です。
江戸時代には、食べ物や地名に洒落を効かせた当て字が多く使われ、心太もその流れにあります。語感の面白さや形状のユニークさがその名の由来とも言われています。
紅白饅頭の意味と由来とは?にも見られるように、江戸時代は食文化に「意味」と「縁起」が込められていた時代だったのです。
ところてんの魅力と栄養面
ところてんは、味そのものは淡白ですが、食感が独特で、つるつる・ぷるぷるとした涼しげな喉ごしが魅力です。
栄養面では、低カロリーで食物繊維が豊富なため、ダイエットや便通改善にも一役買います。
- 100gあたりのカロリーは5kcal前後。
- 天然の水溶性食物繊維を多く含む。
私も子どもの頃、祖母が作ってくれたところてんを黒蜜で食べるのが大好きでした。ちなみに東日本では酢醤油、西日本では黒蜜が主流といった地域差もあります。
日本の五節句とは?と合わせて読めば、ところてんが日本の季節文化とどう関わってきたかがより深く理解できます。
まとめ
ところてんは、奈良時代から続く日本の伝統的な食品であり、寒天やゼリーとは原料も製法も異なる独立した食文化の一部です。
名前の由来や地域ごとの食べ方にも歴史的背景があり、ただの冷たいデザートではない深い魅力があります。ぜひ今年の夏は、改めて「ところてん」を味わってみてはいかがでしょうか。
【上原本店 こだわりの 下町ところてん (120g×20袋セット) 】(薬味、つゆ付)
Amazonで見る