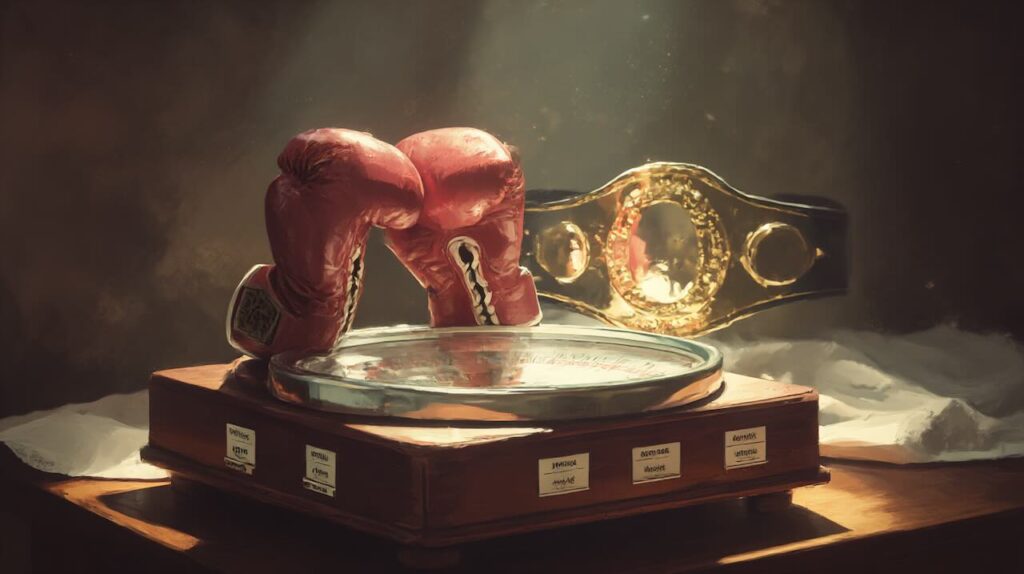100m走や200m走の選手って、みんな筋肉ムキムキ。まるでボディビルダーのような体型に驚いたことはありませんか?
一方で、マラソンや駅伝の選手はスリムな印象。走る競技なのに、体つきがここまで違うのはなぜなのでしょうか?
この記事では、「短距離選手=マッチョ」というイメージの理由を、筋肉の仕組みやトレーニング理論を交えて、わかりやすく解説します。
結論:一瞬の力を最大限に発揮するために“速筋”が必要
短距離走は、ほんの数秒で勝負が決まる競技。
スタートの加速、トップスピードの維持、ゴールまでの爆発的な推進力――これらすべてに必要なのが、「速筋(白筋)」という瞬発系の筋肉です。
この速筋を徹底的に鍛えるためには、高強度の筋トレやスプリント練習が欠かせません。
結果として、筋肉が太く発達し、マッチョな体型になっていくのです。
速筋と遅筋の違いとは?
人の筋肉は、大きく分けて以下の2種類に分けられます。
- 速筋(白筋)
- 短時間で大きな力を発揮
- 瞬発力が必要な競技(短距離、ジャンプ、重量挙げなど)に向いている
- 遅筋(赤筋)
- 長時間の運動に強く、疲れにくい
- 長距離走や登山、水泳など持久系競技に適している
速筋は主に下半身の筋肉――とくに太ももやお尻、ふくらはぎに多く分布しています。
たとえばヒラメ筋とは?名前の由来・場所・役割・鍛え方まで徹底解説!でも紹介しているように、ヒラメ筋は瞬発力と持久力の両面に関わる重要な筋肉です。
なぜ筋肉を大きくする必要があるのか?
ただ速く走るだけなら細くてもよさそうに思えますが、筋肉量が多いほど、以下のようなメリットがあります。
- スタートダッシュで地面を強く蹴る力
- フォームの安定性(姿勢保持)
- 一歩ごとの推進力の最大化
つまり、ただ走るのではなく、「効率よく・速く」走るための“機能的な筋肉”が必要なのです。
マッチョに見えるけど、ただの筋トレではない
短距離選手の筋トレは、ボディビルのような見た目重視ではなく、あくまで競技のための“実用筋”をつくるものです。
そのため、筋トレ内容も実戦的。
たとえば:
- スクワット、デッドリフト(下半身の爆発力)
- ベンチプレス(腕ふりや体幹の安定)
- クリーンやスナッチ(全身の連動性)
これらの筋トレは、テストステロンとは?男性ホルモンの役割と効果、増やす方法まで徹底解説でも触れているように、筋肥大だけでなくホルモン分泌にも良い影響があります。
「走っていれば筋肉がつく」は半分正解
確かにスプリント練習自体も高強度ですが、それだけであそこまでの筋肉はつきません。
短距離選手は、意図的にウェイトトレーニングを取り入れ、部位ごとに鍛え分けています。
一方で、有酸素運動や軽い運動中心のジョギングとランニング、筋トレやダイエットに効果的なのはどっち?目的別に徹底解説でもわかるように、筋肥大を目的としない運動では、筋肉はあまり大きくならない傾向があります。
長距離選手はなぜスリム?
マラソンなどの長距離競技では、軽い体が有利です。
遅筋中心のトレーニングで、無駄な筋肉は極力つけず、酸素効率を最優先にした体づくりが行われます。
同様に、全身運動で効率的に脂肪を燃焼させる縄跳びダイエットは本当に痩せる?消費カロリーと他の運動と徹底比較!では、瞬発力よりもリズムや持久力が重視されます。
まとめ
- 短距離走の選手がマッチョなのは、速筋を鍛える必要があるから
- 筋トレは競技力向上のための手段であり、見た目重視ではない
- 走るだけではなく、戦略的に筋肉を育てている
- 長距離との違いは、瞬発力 vs 持久力の差
- 短距離選手の筋肉は「機能美」。目的に合わせた最適な体づくりの結果
オリンピックや世界陸上を観るときは、選手の筋肉の付き方にも注目すると、見方が一段と深まるかもしれませんね。
走り革命理論 今まで誰も教えてくれなかった「絶対に足が速くなる」テクニック
Amazonで見る