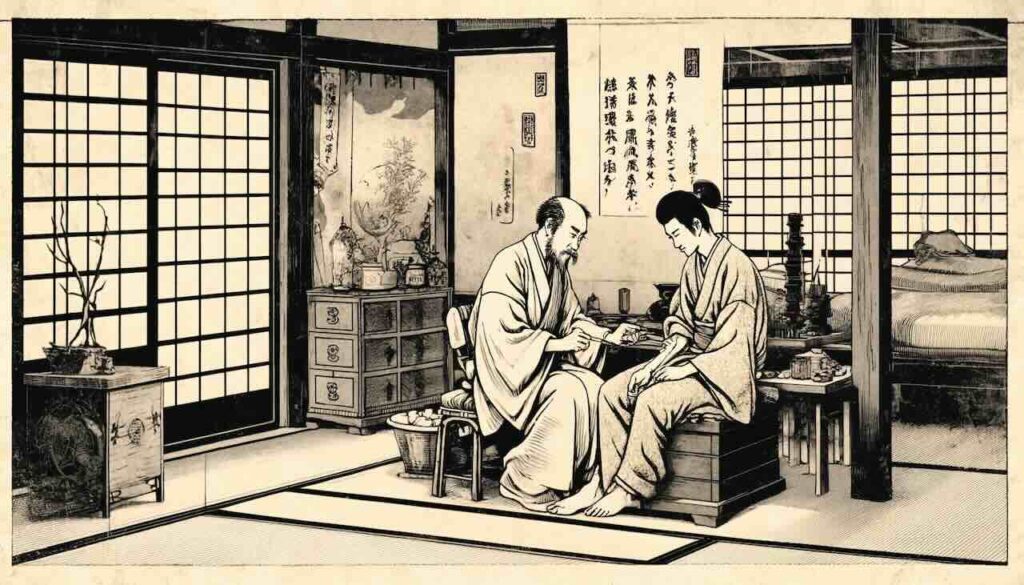「江戸から京都まで500kmをわずか数日で走る」
そんな驚異のスピードを実現していたのが、江戸時代の通信を支えた「飛脚(ひきゃく)」です。
現代の郵便制度が整うはるか昔、情報や物資の伝達に欠かせなかった彼らは、まさに“走るプロフェッショナル”。この記事では、飛脚の仕組み・訓練・スピードの秘密まで、わかりやすく解説します。
飛脚とは?江戸時代の“走る通信インフラ”
飛脚とは、江戸時代に公的・私的な通信を担っていた専門の走者です。
幕府や大名の命令・書状から、商人の荷物や手紙まで、あらゆる重要な物を運んでいました。
- 公用の「公儀飛脚」:幕府や役所の命令書・金銀など
- 民間の「町飛脚」:商人の手紙や荷物、一般庶民の通信
- 大名の「大名飛脚」:各藩専属の通信手段
情報の記録・伝達手段の歴史的背景としてはカメラの起源は紀元前って本当?写真の歴史と日本への伝来をわかりやすく解説、で解説しています。
どのくらい速かったの?
飛脚の速さはまさに超人級。
- 1日で100km以上走破
- 江戸〜京都 約500kmを5〜6日で到着
- 昼夜問わず交代制で走り続ける“継走”システム
これは現代のマラソンランナーにも匹敵する速度です。
江戸時代のインフラが未整備だったことを考えると、その機動力の高さには驚くしかありません。
飛脚が速かった3つの理由
1. 身軽な装束と荷物の最小化
飛脚は「脚絆」「草鞋」など動きやすい軽装で、荷物もできる限り小さくまとめました。
「重いものは持たない、走るための服装」が徹底されていたのです。
2. 宿場リレー式の中継方式
「ひとりで全部走る」のではなく、宿場ごとに担当が交代する中継システムが採用されていました。
- 各宿場の飛脚問屋が拠点
- 1人あたりの距離は10〜20km
- 荷物は専用の木箱や袋でバトンタッチ
このリレー方式により、昼夜を問わず途切れない通信が実現していました。
3. 専門的な訓練と肉体強化
飛脚たちは日々トレーニングを欠かしませんでした。
- 山道での走り込み
- 荷物を背負った状態での長距離走
- スピード変化を想定したインターバル走
- 暑さ・寒さに耐える気候訓練
これはまさに「江戸時代のアスリート」と言っても過言ではありません。
昼夜を問わず走る仕組みとは?
飛脚は、太陽のある時間に限らず、夜でも走ることが多くありました。
- 宿場での交代制により、常に誰かが走っている状態を維持
- 簡易な食事と短い仮眠でスタミナを維持
- 足に負担をかけないための独特な走法(「忍び足走り」など)も
特に急ぎの“早飛脚”は、江戸〜大阪間を3日で往復する記録も残っています。
飛脚と近代郵便のつながり
明治時代に入り、欧米式の郵便制度が整うまで、飛脚は日本の“情報網”を支えていました。
その役割やネットワーク、配達の制度は、のちの郵便制度や宅配便の原型にもなっています。
飛脚問屋の制度やルールは、現代の「集配拠点」「物流の中継所」と非常によく似ており、まさに江戸時代の通信インフラといえる存在です。
まとめ:飛脚は江戸時代の“通信の命綱”だった
- 圧倒的な走力とリレーシステムで、当時の日本をつなぎ続けた飛脚
- 軽装+中継方式+訓練の三拍子がその速さの鍵
- その仕組みは、現代の通信や物流にも影響を与えている
飛脚の存在を知ることで、江戸時代の人々の知恵・工夫・体力のすごさを実感できます。