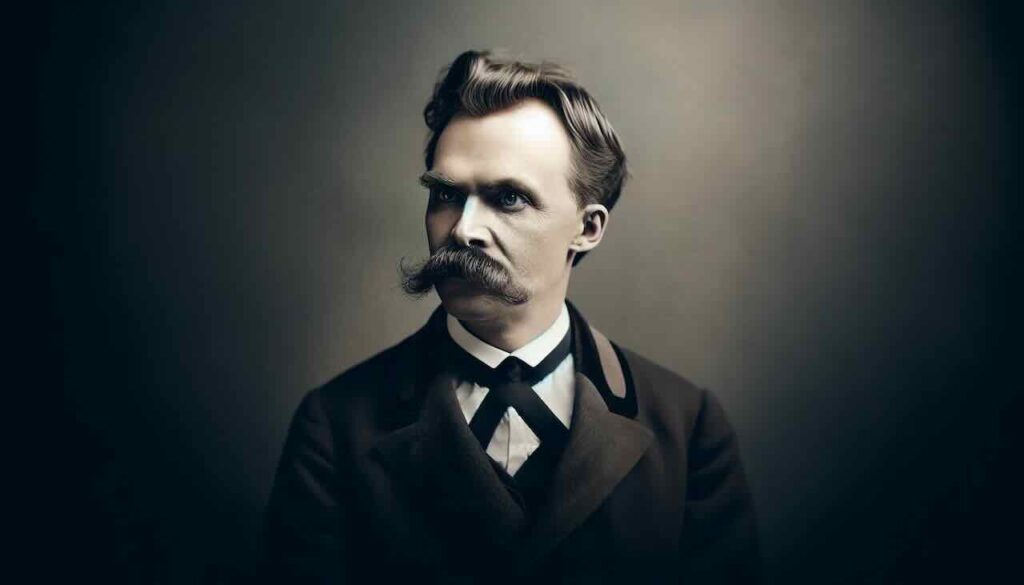「今日は火曜日だから…」「週末まであと2日」──私たちの生活に深く根ざしている「曜日」という考え方。けれど、ふと考えると不思議ですよね。なぜ7日で1週間なのか?曜日の順番や名前はどう決まったのか?この記事では、曜日の起源から日本への伝来、英語との違いまでを、わかりやすく解説していきます。
結論:曜日のルーツは古代バビロニア、日本には6世紀に伝来
・曜日の起源は紀元前7世紀の古代バビロニアにさかのぼる
・ローマ帝国が曜日名を整備し、それがヨーロッパ全体へ広がった
・英語の曜日はローマ神話+ゲルマン神話の影響を受けている
・日本では6世紀の飛鳥時代に中国経由で七曜制が伝わった
古代バビロニアで始まった「七曜制」
「曜日」のルーツは、紀元前7世紀ごろの古代バビロニア(現イラク南部)にあります。当時の人々は、夜空に見える「動く星」──太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星を特別な存在とし、それぞれを神として信仰していました。そして、これらの天体に1日ずつを割り当てて、7日で1サイクルとする「七曜制(しちようせい)」を考案したのです。
ローマ帝国で確立された曜日名
バビロニアの七曜制は、後にギリシャやローマにも伝わり、紀元前1世紀頃のローマ帝国で曜日名が確立されました。ローマでは以下のように、それぞれの曜日に神々を対応させました:
- Sunday(日曜):太陽の神ソル(Sol)
- Monday(月曜):月の女神ルナ(Luna)
- Tuesday(火曜):戦の神マルス(Mars)
- Wednesday(水曜):商業の神メルクリウス(Mercury)
- Thursday(木曜):雷神ユピテル(Jupiter)
- Friday(金曜):愛と美の女神ウェヌス(Venus)
- Saturday(土曜):農耕神サトゥルヌス(Saturn)
これらが後にゲルマン文化圏へと伝わる際、ローマ神話の神々の名前が、ゲルマン神話の神々に「置き換えられた」のが英語の曜日の由来です。
たとえば:
- Tuesday:マルス → ゲルマン神話の軍神ティウ(Tiw/Tyr)
- Wednesday:メルクリウス → 主神オーディン(Woden)
- Thursday:ユピテル → 雷神トール(Thor)
- Friday:ウェヌス → 女神フレイヤまたはフリッグ(Freya/Frigg)
このように、英語の曜日名にはローマとゲルマン(北欧)両神話の影響が混ざっているのです。
日本には6世紀に伝来:七曜の思想と陰陽五行
日本には6世紀の飛鳥時代、中国や朝鮮半島を経由して七曜制が伝来しました。仏教とともに陰陽五行思想や暦の概念が輸入され、その一環として「曜日」も広まったとされています。
ただし当時は、現在のように日常生活で使われるのではなく、占いや天文学的な意味合いが強いものでした。本格的に庶民の生活に曜日が定着したのは、江戸時代後期〜明治時代以降と言われています。
七曜の「日・月・火・水・木・金・土」は、それぞれ対応する天体(太陽、月、火星、水星、木星、金星、土星)から名付けられたもので、中国の影響を強く受けています。
この点については、「二十四節気って何?どういう意味がある?具体的にいつ?わかりやすく解説。」や「農業暦って何?いつからあるの?どうやって決めたの?わかりやすく解説。」といった暦に関する記事でも詳しく解説しています。
まとめ:曜日は古代と現代をつなぐ知的遺産
私たちが毎日何気なく使っている「曜日」は、実は古代バビロニアの天文学と神話、ローマ帝国の文化、そして中国・日本の思想が複雑に重なって生まれた知的遺産です。
英語・日本語で呼び方が違っても、その背後には同じ7つの天体の存在があります。歴史と神話に思いを馳せながら、今日という1日を少しだけ特別な気持ちで過ごしてみてはいかがでしょうか。