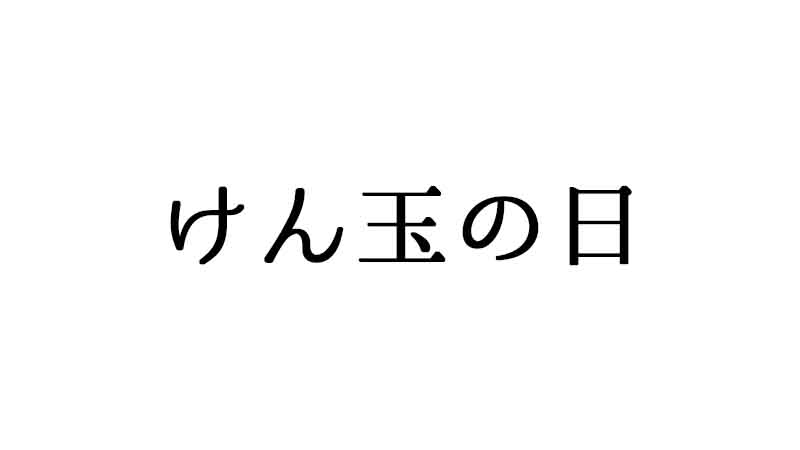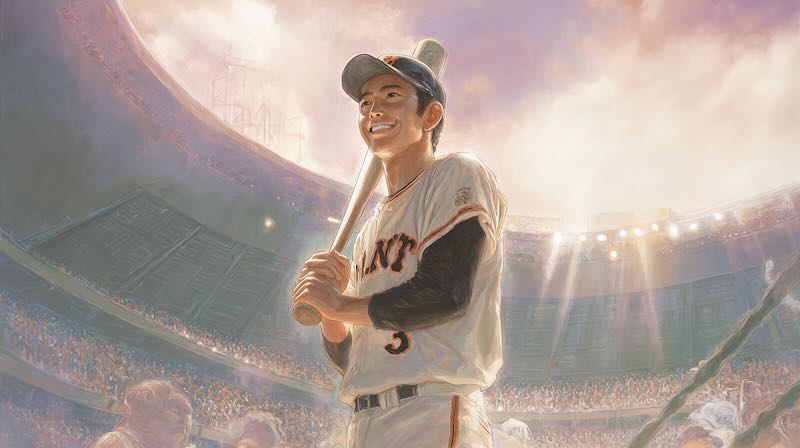5月14日は「けん玉の日」。
「なんで今さらけん玉に記念日が?」「昔よく遊んだけど、今はどうなってるの?」と感じた方も多いかもしれません。
実はこの記念日、日本発祥のけん玉が世界的に注目されている今だからこそ生まれた、とっておきの“文化の日”なんです。
この記事では、けん玉の日の由来や意味、雑学や楽しみ方まで、現代人にも伝わるかたちでわかりやすく紹介します!
結論:けん玉の日は、日本の遊び文化が世界に広がった証
- 5月14日は、けん玉の近代形を生んだ江草濱次(えぐさ・はまじ)の誕生日
- 提唱:一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク(GLOKEN)
- 登録年:2017年、日本記念日協会により公式認定
- 目的:けん玉の魅力を国内外に発信し、日本文化として再認識してもらうこと
なぜ5月14日?けん玉の進化と江草濱次の功績
けん玉の日の由来は、けん玉の“今の形”を生み出した人物、江草濱次の誕生日(5月14日)。
- 大正時代、山口県で「日月ボール」という遊具を改良
- 現代のけん玉の基本構造を考案
- 全国へ広がり、戦後は日本けん玉協会が成立
この誕生日を記念して、2017年にGLOKEN(グローバルけん玉ネットワーク)が記念日登録しました。
けん玉ってどんな遊び?
けん玉は、玉(たま)を剣(けん)で刺したり、皿で受けたりする木製の遊び道具です。
- 剣先:玉を刺す部分
- 大皿・小皿・中皿:玉を受け止める場所
- 玉:ひもで繋がれた球体
シンプルながら奥が深く、集中力・バランス・反射神経を使う“アナログなのにスポーツ性が高い”遊びです。
実はフランス生まれ?けん玉の意外なルーツ
けん玉の原型は、17〜18世紀のフランスで「ビル・ボケ(bilboquet)」と呼ばれていた木製玩具だとされています。
- 江戸時代に日本に伝来
- 明治〜大正時代に改良
- 昭和以降に競技化・段位制導入
今では日本の伝統文化のひとつとして、「折り紙」などと並んで紹介されることも。
詳しくは「折り紙の世界的な人気と起源」も参考になります。
競技けん玉や世界大会も盛ん!
日本けん玉協会による段位制度や大会に加え、海外では「KENDAMA」としてブームに。
- アメリカ・ヨーロッパで若者に人気
- ストリートカルチャーやスケートボードと融合
- 技を競うYouTube動画も多数再生
けん玉は今や、“技を極めるスポーツ”としての側面も持っています。
GLOKENとは?けん玉の日の提唱団体
「グローバルけん玉ネットワーク(GLOKEN)」は、日本の伝統文化としてのけん玉を国内外に発信する団体です。
- 国際大会の主催
- 海外交流イベント
- 世界への技術・文化の発信
けん玉の日の制定をきっかけに、**「遊び」から「文化・教育・国際交流」へと活動を広げています。
けん玉が持つ3つの魅力
- 集中力・運動能力アップ
- 遊びながら脳と身体を刺激
- 世代を超えて楽しめる
- 親子・祖父母・友人といつでも勝負できる
- 文化と競技の融合
- 日本文化を伝えつつ、スポーツとしても世界とつながる
けん玉は、歌舞伎や俳句などと同じように「日本の伝統芸能」の一部としても評価されています。
けん玉の日にやってみたいこと
- 子どもの頃を思い出して、技に再挑戦
- SNSで #けん玉の日 で検索して動画を見てみる
- 海外で流行している技や大会の様子をチェック
- 家族で「誰が一番うまいか対決」してみるのも楽しい!
まとめ:けん玉の日は、日本の遊び文化を世界とつなぐ記念日
- 5月14日は「けん玉の日」
- 由来は近代けん玉の生みの親・江草濱次の誕生日
- 提唱団体:グローバルけん玉ネットワーク(GLOKEN)
- けん玉は今、世界で“日本文化×スポーツ”として進化中
テレビやスマホから少し離れて、今日はけん玉を手に取ってみませんか?
遊びながら、日本の“文化の奥深さ”に触れられるかもしれません。