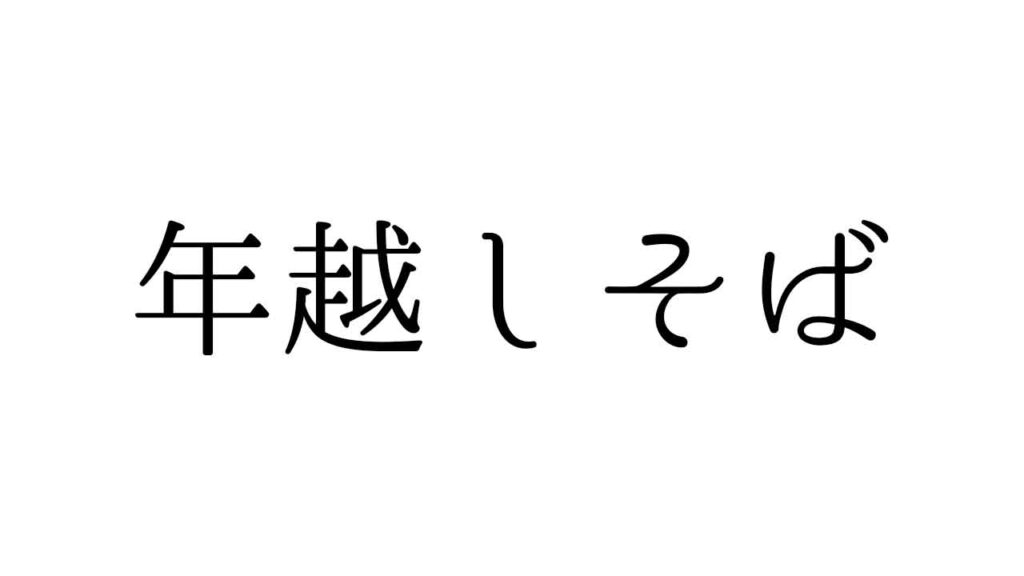年末になると各地の寺院から聞こえてくる除夜の鐘。静かな夜に響くその音は、日本の大晦日を象徴する風物詩とも言える存在です。
でも、「なんで108回も鐘を鳴らすの?」「除夜ってどういう意味?」「日本だけの習慣なの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、除夜の鐘に込められた意味や由来、各地での違いまで、年越しの夜に知っておきたい情報をやさしく解説します。
除夜の鐘とは?
「除夜(じょや)」とは、一年の最後の夜――つまり大晦日のこと。
その夜に寺院で鳴らされる鐘が「除夜の鐘」です。
日本では多くの寺で、大晦日から元日にかけて鐘を108回打ち鳴らすのが一般的で、これは新年を迎える大切な宗教的・文化的行事として長く親しまれています。
なぜ108回なのか?仏教に基づく深い意味
108という数字は、仏教における人間の煩悩の数とされています。煩悩とは、欲望・怒り・迷いなど、人の心を乱す感情のこと。
以下のように数えられます:
- 人には六根(目・耳・鼻・舌・身・意)があり
- それぞれが「好・悪・平(好き・嫌い・どちらでもない)」という感情を持ち
- さらに「過去・現在・未来」の三つの時間軸で考えると…
6 × 3 × 3 = 54
さらに、仏教の根本的な迷いの原因とされる三毒(貪・瞋・癡)と組み合わせることで、54 × 2 = 108の煩悩があるとされるのです。
除夜の鐘は、これらの煩悩を一つずつ打ち払うという意味を持っています。
除夜の鐘は日本だけの文化?
実は、大晦日に鐘を鳴らす文化は中国や韓国などアジアの仏教国にもあります。
例えば、韓国の「普信閣(ポシンガク)」では、天界の数を表す33回鐘を鳴らす風習があります。
しかし、108回という回数や、誰でも参加できる形式は日本独自の発展であり、年末の大衆的な宗教行事として世界でも珍しいものです。
除夜の鐘の歴史と始まり
文献によると、除夜の鐘は鎌倉〜室町時代には既に一部の寺で行われていたとされ、江戸時代に全国的に広まったと考えられています。
特に年末年始に寺を訪れ、一年を振り返って煩悩を清めるという風習が民衆に定着し、今日のスタイルへとつながっていきました。
鐘を鳴らす時間と流れ
多くの寺では、12月31日の夜11時ごろから開始し、午前0時までに108回を鳴らし終えるのが一般的です。
地域や寺によっては、参拝者が1人1回ずつ打つところもあれば、僧侶だけで一斉に鳴らす形式もあります。
鐘を打つマナーと心構え
参加できる寺では、以下のマナーを守りましょう:
- 静かに列に並び、私語を慎む
- 打つ前後には一礼する
- 丁寧に、力任せに叩かず静かに鳴らす
- 他の参拝者への気配りを忘れずに
除夜の鐘と年末年始の文化的つながり
除夜の鐘は、単なる鐘の音ではなく、一年の穢れを払い、清らかな気持ちで新年を迎えるための儀式です。
この「気持ちを整える」文化は、他の年末行事にも共通しています。
たとえば、
こうして、除夜の鐘はそれらすべてを締めくくる“精神的なクライマックス”とも言えるのです。
まとめ
除夜の鐘は、煩悩を払う仏教的な意味と、年末年始を大切に迎える日本人の精神文化を象徴する行事です。
その108回には、「一年を振り返り、心を整えて、新しい年をまっさらな気持ちで始める」という強い願いが込められています。
慌ただしい年の瀬だからこそ、静かに鐘の音に耳を澄まし、心を整える――そんな時間を大切にしたいものです。
だれでもわかる ゆる仏教入門
Amazonで見る