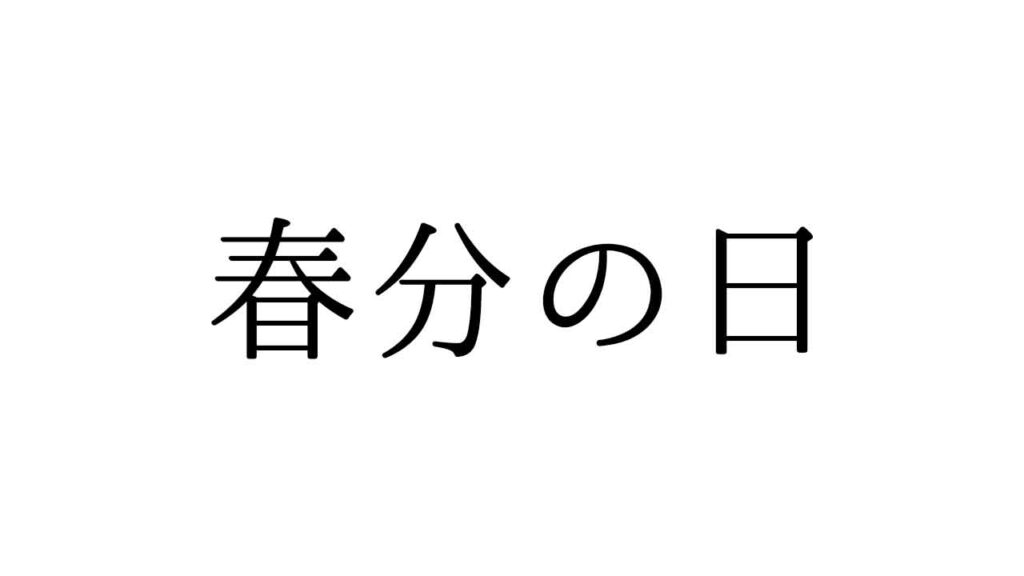「春分の日って、なにをする日なんだろう?」
「昼と夜が同じ長さって本当?」
そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか?
春分の日は、自然と生命に感謝する日であると同時に、ご先祖様とのつながりを再確認する日本独自の文化的な祝日でもあります。
この記事では、春分の日の意味・由来・歴史から、具体的な過ごし方、さらに2025年から2030年までの春分の日の日付一覧まで、わかりやすく解説します。
春分の日とは?昼と夜の長さが同じになる日
春分の日(しゅんぶんのひ)は、太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。
日本ではこの日を境に、春が本格的に始まるとされ、気温や日照時間も徐々に変化していきます。
1948年に「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として国民の祝日に制定され、現在に至ります。
2025年〜2030年の春分の日はいつ?
年によって若干変動しますが、春分の日は通常3月20日または21日になります。
| 年度 | 春分の日 |
|---|---|
| 2025年 | 3月20日(木) |
| 2026年 | 3月20日(金) |
| 2027年 | 3月21日(日) |
| 2028年 | 3月20日(月) |
| 2029年 | 3月20日(火) |
| 2030年 | 3月20日(水) |
この日を中心とした1週間は、仏教の「お彼岸」にあたります。春のお墓参りのタイミングとしても広く親しまれています。
春のお彼岸については、お彼岸とは?お墓参りの意味と時期、そして由来を解説 もあわせてご覧ください。
春分の日の由来と背景:農業・仏教との深いつながり
古代の農業暦と春分
古代の日本では、春分は農業の始まりの合図とされていました。ちょうど種まきの時期であり、太陽の動きを基準に五穀豊穣を祈願する風習が各地に広がっていたのです。
このような暦の知恵は、日本の伝統的な「農業暦」とも結びついています。
仏教における「彼岸の中日」
春分は、仏教でいう「彼岸(ひがん)」の中日(ちゅうにち)にあたります。この世(此岸)と悟りの世界(彼岸)がもっとも近づくとされる日であり、先祖供養に適した日と考えられてきました。
春分の日の過ごし方
春分の日は、以下のような日本らしい過ごし方が根付いています。
- お墓参りをする
- 春のお彼岸の一環として、多くの家庭で先祖の墓を訪れ、感謝を伝えます。
- ぼたもちを食べる
- 「ぼたもち」は春のお彼岸の定番。もち米にあんこをまぶした食べ物で、秋分の日の「おはぎ」とほぼ同じです。
- 自然に親しむ
- 春の訪れを祝い、草花を楽しんだり、散歩をしたり、公園でゆっくり過ごすのもおすすめです。
- 春の季節感を楽しむ
- 桜の開花が近づき、各地で春の訪れを感じる季節。三色団子や春の和菓子を楽しむ家庭も増えています。
春分の日と昼夜の関係:本当に同じ長さ?
天文学的に春分の日は、太陽が赤道上を通過する瞬間=「春分点」を通る日です。この日を境に、北半球では日が長くなっていきます。
ただし、実際の昼の方がやや長くなるのは、大気の屈折や太陽の見かけ上の位置の影響です。
「春分」「秋分」などを含む暦と太陽の関係は、
二十四節気とは?意味・由来・活用法までわかりやすく解説 で詳しく紹介しています。
まとめ:春分の日は自然と命に感謝する大切な祝日
春分の日は、昼と夜が等しくなるだけでなく、農業、仏教、自然への感謝など、日本文化のさまざまな要素が凝縮された日です。
春の訪れを祝い、先祖に手を合わせる——
そんな心静かな一日を過ごしてみるのはいかがでしょうか?
春分の意味を知ると、この祝日がもっと味わい深いものになります。
誰かに話したくなる 日本の祝日と歳事の由来
Amazonで見る