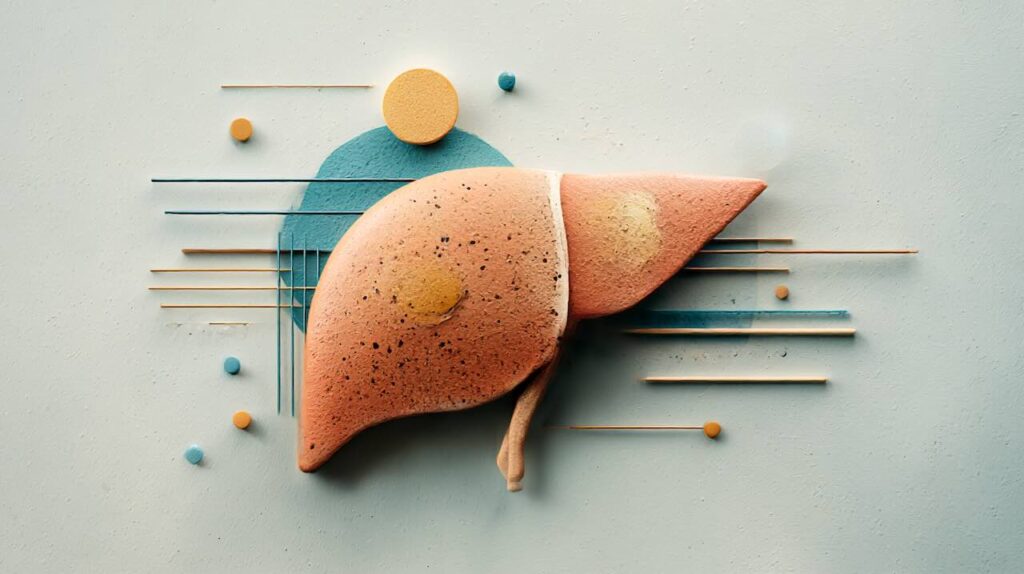朝起きて「全然動いていなかった気がする…」とか、「何度も寝返りしてたかも?」と思ったこと、ありませんか?
実はこの“寝返り”には、体や睡眠の質に関わる大切な意味があるんです。
「寝返りが多いと睡眠の質が悪いの?」「全然動かないのは良いこと?」といった疑問にも、科学的な観点からやさしく解説していきます。
この記事を読むことで、自分にとって最適な“寝返り”と睡眠環境の整え方がわかりますよ。
結論:寝返りは必要な調整動作。多すぎ・少なすぎの両方に注意
人は誰でも寝返りを打っていますが、その回数やタイミングは個人差が大きく、環境や体調によっても左右されます。
平均的な回数は 一晩に20〜30回程度。
ただし、少なすぎると血流不良や床ずれの原因に、多すぎると眠りの質が下がっているサインになることも。
大切なのは、「寝返り=悪」ではなく、「体の自然な調整」と理解することです。
寝返りが起こるタイミングと理由
眠りの浅いタイミングに多い
寝返りは主に、レム睡眠や浅いノンレム睡眠中に多く起こります。
深い眠り(徐波睡眠)のときは動きがほとんどなく、眠りが浅くなったときに体をリセットするように自然と動くのです。
なぜ寝返りが必要なのか?
- 血流の確保
同じ姿勢が続くと血流が滞り、筋肉が硬直します。寝返りは体圧を分散し、血行を助けます。 - 湿度・温度の調整
人は寝ている間に大量の汗をかくため、動かないと蒸れたり冷えたりする原因に。 - 関節と筋肉の保護
長時間の圧迫による痛みや疲労を防ぐためにも、定期的な寝返りが効果的です。 - 自律神経のバランス調整
寝返りは交感神経と副交感神経の切り替えにも関与し、自然な睡眠リズムを支えています。
寝返りが多すぎる/少なすぎるときのサイン
多すぎる場合(50回以上)
- マットレスが合っていない(硬すぎ・柔らかすぎ)
- ストレスや不安感
- 睡眠時無呼吸症候群や浅い眠りの連続
- 室温・湿度が適切でない
→ このような環境が影響している可能性があります。
「寝ているのに疲れが取れない」と感じる方は、寝る直前に落ちる感覚の正体と改善策もチェックしてみてください。
少なすぎる場合(ほとんど動かない)
- 高齢による筋力・柔軟性の低下
- 睡眠薬やアルコールによる過剰な沈静
- 疾患による動作制限
- 長時間の同一姿勢による床ずれリスク(特に介護現場)
年齢による寝返りの傾向
- 子ども:成長ホルモンの関係で睡眠が浅くなりやすく、寝返りも多い
- 高齢者:筋力の低下により少なくなりがち。ただし血流確保のために工夫が必要
快適な寝返りのための寝具・環境
マットレス
- 反発力が適度にあるもの:押し返しで寝返りがしやすくなる
- 体圧分散性が高いもの:特に腰・肩などへの負担を減らす
- 素材例:高反発ウレタン・ラテックス・ポケットコイル
その他のポイント
- 枕の高さ・硬さも寝返りに影響
- 室温は20〜22℃、湿度は50〜60%が理想
- 遮音や照明環境にも配慮を
寝返りが健康に与える影響
寝返りは、「ただの動き」ではなく、私たちの体と心のコンディションに密接に関わっています。
実際、食後の眠気とその対策でも紹介されているように、睡眠の質を高めるには、体内のバランスをうまく整える工夫が必要なのです。
まとめ
- 寝返りは体の自然な調整動作であり、健康な睡眠の一部
- 多すぎ・少なすぎは、寝具や環境、体調のサインかも
- 年齢や体調に合わせて、寝具や環境を最適化しよう
- 自分の寝返りの傾向を知ることで、快適な眠りに一歩近づける
睡眠に関するちょっとした知識を取り入れるだけでも、毎日のパフォーマンスが変わってきますよ。
AooDen 枕 低反発 首が痛くならない まくら 低め高め選択可能 横向き寝 仰向け寝 通気性 pillow ストレートネック カバー洗濯可 低反発枕 高め 低め 三層構造 プレゼント 56285.5/10.5cm
Amazonで見る