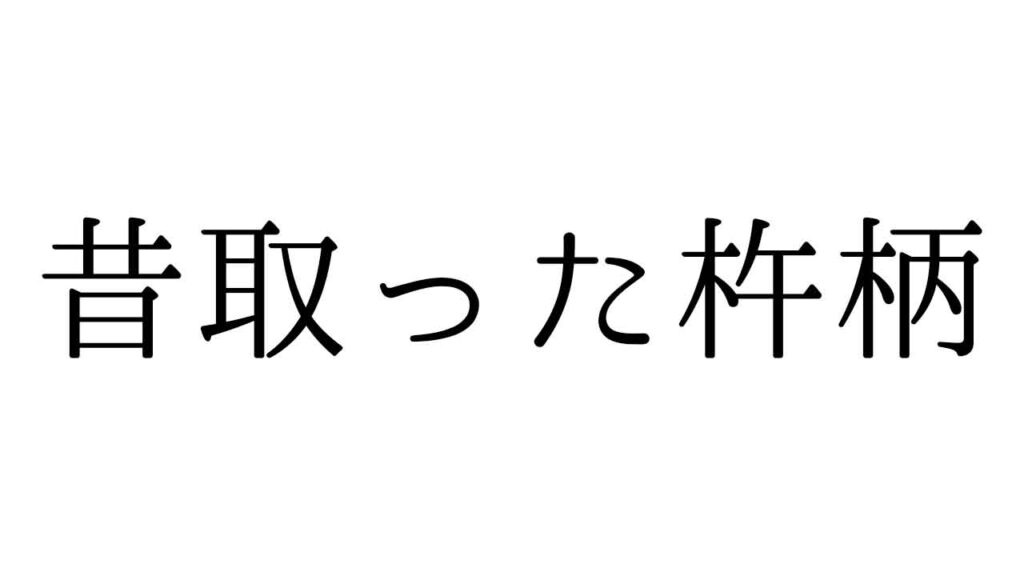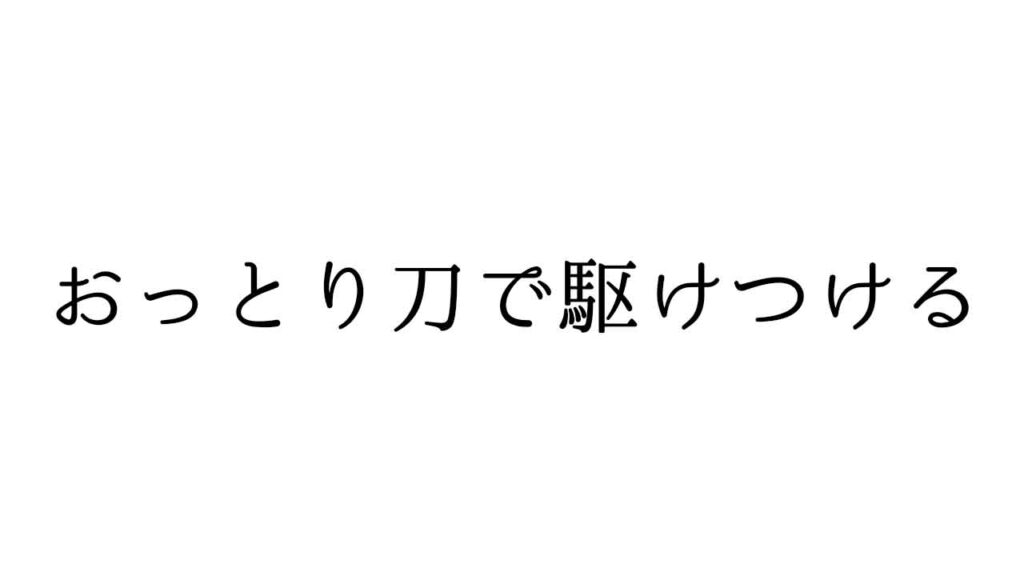「昔はよくやってたんだけどね…」
そんな一言から始まる話って、意外と今の自分に役立つことがあります。
「昔取った杵柄(むかしとったきねづか)」ということわざも、まさにそんな“眠っていた力”が再び輝く瞬間を表現した日本語の知恵です。
結論:「昔身につけた技術や経験は、時間が経っても役立つ」
このことわざの意味はとてもシンプルです。
「若いころに習得した技能や経験は、長いブランクがあっても、ふとした時に活きてくることがある」
たとえば、昔ギターを弾いていた人が、何年ぶりかに触ったら自然に指が動いたり。
元スポーツ選手が、体は衰えていてもフォームや感覚は覚えていたり。
そういう「眠っていた才能」が顔を出す瞬間にぴったりの表現です。
「杵柄(きねづか)」って何のこと?

「杵(きね)」とは、餅をつくときに使う大きな木の棒のこと。
その持ち手の部分が「杵柄(きねづか)」です。
昔の日本では餅つきは大切な年中行事のひとつで、経験者ほど上手にこなせる作業でした。
「昔、杵を握って餅をついていた経験が、年月を経ても自然と体に染みついている」——そんな光景が、この言葉の背景にあるのです。
使い方の具体例
- ブランクがあっても通用する場面
「何年ぶりに卓球したけど、昔取った杵柄で意外と勝てたよ」 - 仕事や趣味で腕前を発揮する場面
「おじいちゃん、昔は大工だったらしくて、棚の修理も昔取った杵柄であっという間だった」 - 人に驚かれるような“隠れた特技”を出すとき
「ピアノなんて子ども以来なのに、昔取った杵柄ってやつで指が勝手に動いたよ」
類似表現・反対表現も覚えておくと便利!
類似表現
- 芸は身を助く
一度身につけた技術や芸事は、将来必ず役に立つという教訓。 - 習うより慣れよ
理屈よりも、実際に経験した方が力になるという意味。
これらは「おっとり刀で駆けつける」の意味とは?意外な由来と使い方をわかりやすく解説のような、文化的な慣用句と併せて理解するとさらに深まります。
反対の意味に近い表現
- 年寄りの冷や水
昔の自信で無理をして、かえって危険な結果になるという注意喚起のことわざです。
現代での応用:転職や復職、趣味の再開にも
- ブランクからの再挑戦に自信が持てる言葉
- シニア世代の能力発掘にもぴったり
- 就職活動で「昔やっていたこと」を強みに変える場面
最近では「塞翁が馬」の意味、語源、使い方を具体例つきで解説のように、人生の転機やリスタートに関することわざとともに、この表現が見直されつつあります。
まとめ:「昔取った杵柄」は眠っていた力に光をあてる言葉
このことわざは、過去に習得したスキルや経験は簡単には消えない、という希望をくれます。
「今さらもう遅いかも…」と思う前に、一度手を動かしてみてください。
意外と体や心が覚えているかもしれません。
人生は長いからこそ、過去の力が未来の助けになる——「昔取った杵柄」は、そんな“時間を超える力”を教えてくれる日本語の知恵です。
小学生のまんが慣用句辞典 改訂版
Amazonで見る