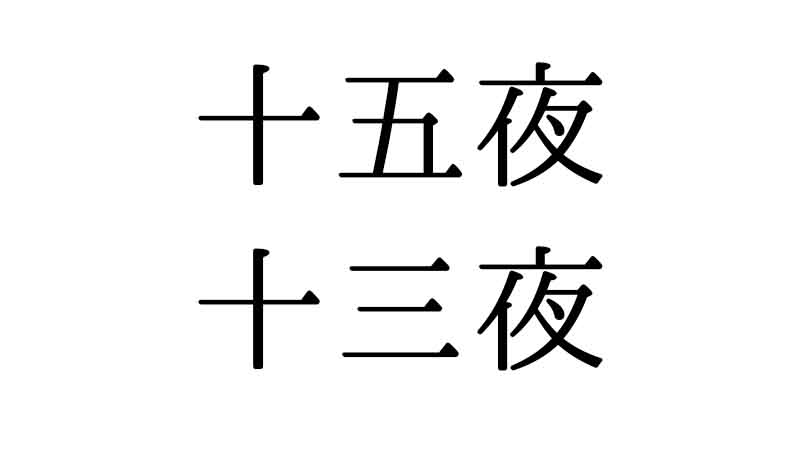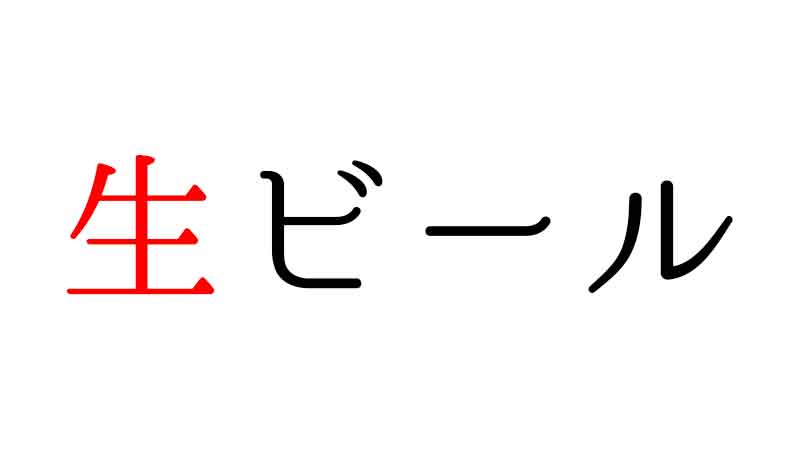「十五夜は知っているけれど、十三夜って何?」と思ったことはありませんか。私自身、子どもの頃は秋になると家族で団子をお供えして「十五夜」を祝っていましたが、大人になってから「十三夜」というもう一つの月見行事があることを知り、驚いた経験があります。実はこの2つの月見にはそれぞれ違った意味と由来があり、日本ならではの文化が息づいているのです。
この記事では、十五夜と十三夜の違い、その由来、なぜ2回月見をするのかを分かりやすく解説します。読み終わるころには、今年の月見がぐっと楽しみになるはずです。
十五夜と十三夜の基本
- 十五夜(中秋の名月)は、中国から伝わった旧暦8月15日の月見行事。
- 十三夜は、日本独自に生まれた旧暦9月13日の月見行事で、「栗名月」「豆名月」とも呼ばれる。
- 十五夜だけ祝うことを「片見月(かたみづき)」と呼び、不吉とされ、両方を祝う風習が広まった。
ちなみに2025年は、十五夜(中秋の名月)が10月6日(月)、十三夜は11月4日(火)にあたります。旧暦の日付だけだと分かりにくいですが、新暦に置き換えると「秋が深まるころに2回月見がある」というイメージがしやすくなります。
十五夜とは?
十五夜は「中秋の名月」とも呼ばれ、旧暦8月15日に行われる月見です。平安時代に中国から伝わり、宮中行事として定着しました。当時は月を愛でながら詩を詠んだり、酒を酌み交わしたりする風雅な文化でした。
現代ではススキを飾り、月見団子を供える風習が残っています。十五夜の月は一年で最も美しいとされ、秋の澄んだ空に映える満月を鑑賞する習慣が今も続いています。
関連知識として「中秋の名月は普通の満月とどう違う?文化的・科学的な違いを徹底解説!」も参考になるでしょう。
十三夜とは?
十三夜は旧暦9月13日にあたる月見行事で、日本独自の文化です。十五夜ほどの満月ではないものの、少し欠けた月が「趣がある」とされ、古来から親しまれてきました。
この日は収穫祭とも結びつき、収穫された栗や枝豆を供えることから「栗名月」「豆名月」と呼ばれます。十五夜に比べて知名度は低いですが、日本ならではの美意識が感じられる行事です。
なぜ2回月見をするのか?
十五夜だけを祝うことを「片見月」と呼び、不吉とされました。そのため、十五夜と十三夜の両方を祝うのが望ましいとされ、2回月見を行う習慣が広まりました。
「一度きりで終わらせず、二度の月見で秋を味わい尽くす」――これが古来の人々の自然観と生活の知恵でもあります。
月見文化の広がり
お月見は日本独自の十三夜だけでなく、世界各地にも似た風習があります。例えば中国では「中秋節」として盛大に祝われます。この違いを知ると、月見文化の奥深さを実感できます。興味のある方は「お月見は日本だけの文化?世界の月見行事とその違いを比較解説」をご覧ください。
また、お月見といえば団子ですが、その数や供え方にも意味があります。詳しくは「お月見はなぜ団子を食べるの?意味・由来・地域差をわかりやすく解説」で解説しています。
まとめ
十五夜は中国伝来の中秋の名月、十三夜は日本独自の栗名月・豆名月。両方を祝うことで「片見月」を避け、秋を二度楽しむ文化が育まれました。
私自身、十三夜を意識するようになってからは、秋の夜空を二度見上げる贅沢を知りました。満ちる月と欠けた月、それぞれに違った美しさがあるのだと気づかされます。今年はぜひ、両方の月を味わってみてください。
萬古焼 置き物 インテリア オブジェ 卓上 飾り 「 日本の歳時シリーズ 」 9月 お月見 部屋飾り 玄関飾り 置物 ミニ コンパクト 日本製 18709
Amazonで見る