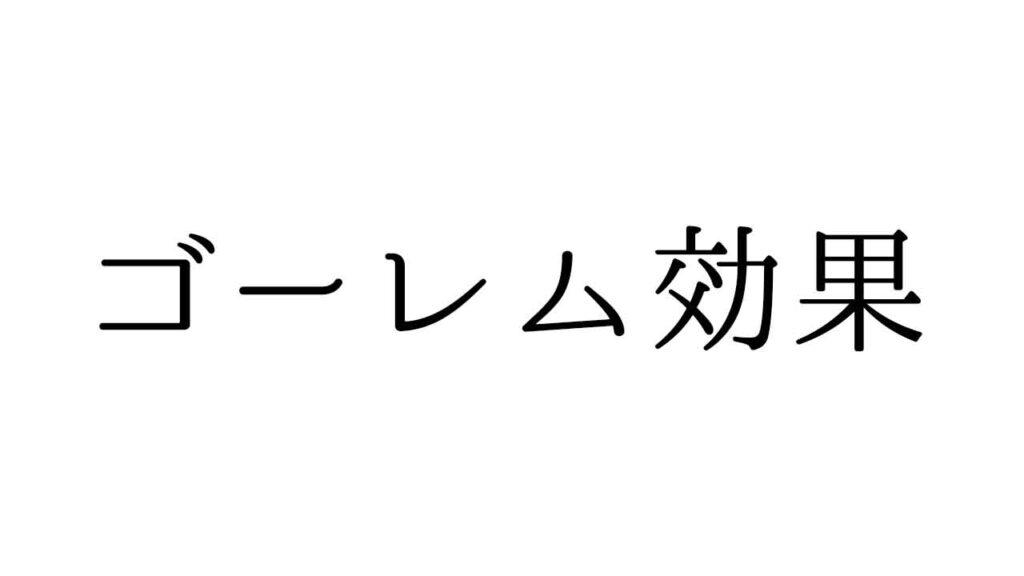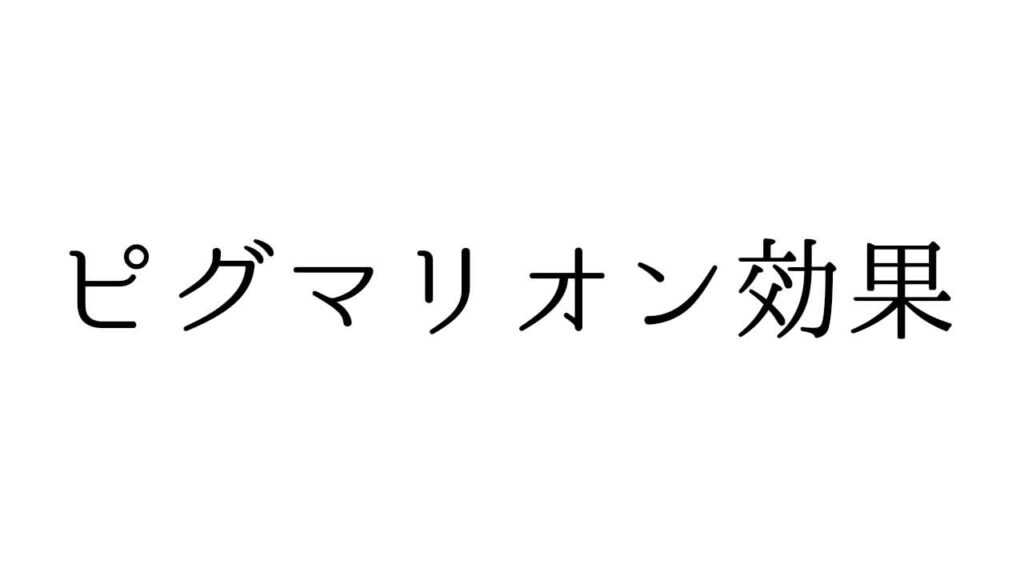「なんとなく期待されていないと、やる気が出ない…」
「周囲の評価が低いと、本当に結果も悪くなる気がする…」
そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか?
実はそれ、心理学で「ゴーレム効果」と呼ばれる現象かもしれません。
この記事では、ゴーレム効果の意味・使い方・提唱者・歴史的背景まで、わかりやすく解説します。教育や職場、人間関係に活かすヒントも紹介します。
ゴーレム効果とは?
ゴーレム効果とは、周囲からの期待が低いと、本当にパフォーマンスが低下してしまうという心理的現象のことです。
つまり、「お前には無理だろう」と思われたり扱われたりすると、本人も無意識のうちに「どうせ無理」と感じてしまい、実力を発揮できなくなるのです。
この現象は、教育や職場など、評価が明確に存在する場面で特に顕著に現れます。
具体例
- 学校で「成績が悪い」と見なされた生徒が、教師から期待されず、本当に成績が伸びなくなる
- 上司が「あいつには難しい」と思って簡単な仕事しか任せないと、本人の成長機会が奪われてしまう
- 親が「この子はおとなしいからリーダーは無理」と決めつけることで、子どもも自信を失う
いずれも、「他人の期待の低さ」が知らず知らずのうちに影響を与え、その通りの結果を引き寄せてしまっているのです。
使い方・どんな場面で使われるの?
「ゴーレム効果」は、主に以下のような場面で使われます。
- 教育現場
- 教師が生徒に対して偏った期待や扱いをすると、学力差が固定化される可能性がある
- 学校教育における公平性や支援の在り方を考えるときに重要なキーワード
- ビジネス・職場
- 上司の期待が部下のモチベーションに大きな影響を与える
- 「この人はできない」というレッテルがパフォーマンスを下げてしまう例として
- 子育て・家庭教育
- 親の期待の仕方が、子どもの自己評価に大きく影響する
- 無意識の「期待しない姿勢」が子どもの可能性を狭めてしまうことも
- 自己理解・内省
- 自分が周囲からどう見られているかを意識することで、行動や成長への影響を再認識できる
誰が言い出した?いつからある?
ゴーレム効果は、1960年代のアメリカの教育心理学者たちによって、ピグマリオン効果(期待が高いと成果が上がる)と対比する形で提唱されました。
特に有名なのが、社会心理学者ロバート・ローゼンタール(Robert Rosenthal)と、教育者レノア・ジェイコブソン(Lenore Jacobson)による研究です。
1968年、彼らは「教師の期待が生徒の成績に影響を与える」ことを証明する実験を行いました。
この実験では、無作為に選ばれた生徒を教師に「成績が伸びる可能性が高い」と伝えただけで、実際に成績が向上したのです。
この研究は「ピグマリオン効果」として有名になりましたが、反対に「期待されない生徒は成績が上がらない」傾向も確認されたことから、これを逆説的に「ゴーレム効果」と名付けたのです。
名前の由来は「ユダヤの伝説」
「ゴーレム」という言葉は、ユダヤ教の伝承に登場する土でできた人造人間の名前に由来します。
ゴーレムは本来、命令されたことしかできず、感情や創造力のない存在とされており、
「他者の思い通りにしか動けない、意志のない存在」という象徴としてこの名前が使われたのです。
つまり、期待されないことによって、人は“ゴーレム”のように行動の自由や可能性を奪われてしまうという意味が込められています。
ピグマリオン効果との違い
| 項目 | ピグマリオン効果 | ゴーレム効果 |
|---|---|---|
| 期待の方向 | 高い期待 | 低い期待 |
| 結果 | 成績・能力が向上する傾向 | 成績・能力が下がる傾向 |
| 原因 | 他者のポジティブな先入観 | 他者のネガティブな先入観 |
| 応用例 | 優秀な部下に期待して育てる | 期待しないことで本人が萎縮する |
どちらも「他者からの期待」が本人のパフォーマンスに影響を与えるという点では同じですが、結果が真逆になる現象です。
ゴーレム効果は「低い期待」によって成果が下がる現象でしたが、その逆に、期待されることで能力が高まりやすくなる心理現象も存在します。
それが「ピグマリオン効果」です。教育・職場・子育てなどにも応用される現象についてはピグマリオン効果とは?意味・使い方・提唱者・実例・ゴーレム効果との違いをわかりやすく解説、を御覧ください。
ゴーレム効果を防ぐには?
ゴーレム効果は、無意識に起きやすいものです。以下のような対策が有効です。
- 先入観を持たずに接する
- 「この人はこういう人だ」と決めつけない
- 小さな成長を見逃さない
- 過去の印象にとらわれず、変化や努力を正しく評価する
- 公平な機会を与える
- 仕事や発言のチャンスを偏らずに提供する
- 自分の“まなざし”に気づく
- 他人への態度や言葉に、無意識の期待やあきらめがにじんでいないか見直す
まとめ
- ゴーレム効果とは、期待されないことでパフォーマンスが下がる心理的現象
- 教育・職場・家庭など、あらゆる人間関係に影響を与える可能性がある
- 名前の由来はユダヤ伝承の「土の人形=ゴーレム」から
- ピグマリオン効果の逆で、「低い期待」が原因となる
- 防ぐには、先入観を持たず、可能性を信じるまなざしが重要
人は、見られ方によって本来の力を発揮できるかどうかが変わります。
「この人はできない」と決めつけずに、誰もが伸びる可能性を持っているという前提で接してみると、驚くような成果につながるかもしれません。
思い通りに人を動かすヤバい話し方
Amazonで見る