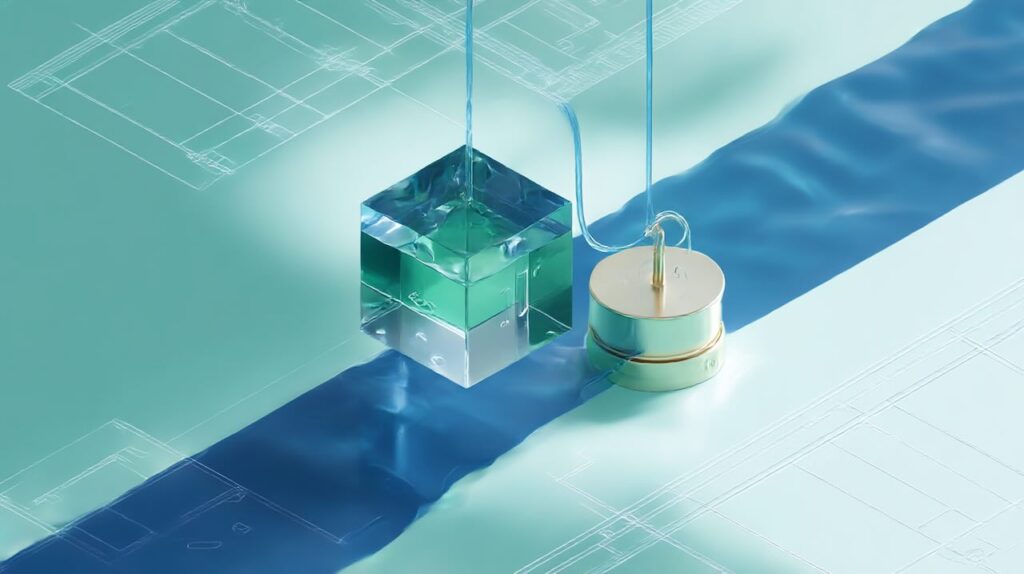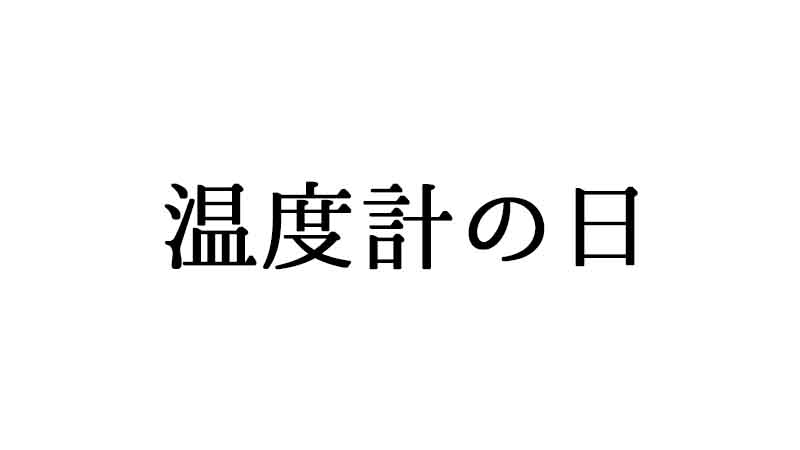「今日はツイてる気がする」「このままじゃ流れが悪くなるかも」──
麻雀やギャンブルを経験したことがある人なら、そんな感覚にとらわれたことが一度はあるはずです。
しかし、その「流れ」とは一体何なのでしょうか? 本当に存在するのでしょうか?
この記事では、「流れ」という曖昧な概念について、科学的な根拠と心理学の観点から徹底的に解説します。
勝ち負けの波に翻弄されないために、冷静な判断力を持つためのヒントにもなります。
「流れ」とは何か?2つの意味
麻雀やギャンブルにおける「流れ」は、主に以下の2つの現象を指して使われます。
- 勝ちや負けが偏って続く状態(運気の連続)
- 自分や相手の精神状態の変化による影響
つまり、流れとは現象と心理が絡み合った“主観的な印象”にすぎないとも言えます。
科学的には「流れ」は存在しない
1. ランダム性と確率の支配
麻雀もルーレットもスロットも、本質的には確率と乱数によって決まるゲームです。
赤が5回連続で出る、良い配牌が続く――そうした現象は確率上、普通に起こり得ることであり、
「流れが来ている」と感じるのは脳の錯覚に過ぎません。
2. ギャンブラーの誤謬(ごびゅう)
これは「今まで負けが続いたから、次は勝つはずだ」と信じてしまう心理的な誤りです。
- サイコロで5回連続で6が出なかったとしても、次も6が出る確率は1/6。
- 過去の結果は、未来の確率に一切影響を与えません。
この誤謬に陥ることで、「流れを変えたい」という誤った意思決定が生まれやすくなります。
※ギャンブルの還元構造や負ける仕組みそのものについては、
「ギャンブルの還元率と負けやすさの本質」で詳しく解説しています。
なぜ「流れ」があるように感じるのか?
1. 精神状態の変化がプレイに影響する
「今日はツイてる」と思えば自信がつき、冷静な判断ができる。
「流れが悪い」と感じれば焦りやミスが増え、さらに負けが続く。
つまり、「流れ」とは感情や思考の連鎖が引き起こす自己暗示的な現象です。
2. 勝っているときほど堅実、負けているときほど無謀
- 勝ちが続くときは慎重になりやすい(守りの意識)
- 負けが続くときは無理な勝負を仕掛けがち(取り返したい欲)
このようなプレイスタイルの変化が、結果として勝ち負けの偏りを生み、
「流れが変わった」という錯覚を強めるのです。
麻雀における「場の流れ」という考え方
麻雀には「一人が連続でアガると、その人に“流れ”が来る」という信仰が根強くあります。
たしかに、連続アガリによって周囲が警戒し、アガっている側は自信を持って攻めるようになるため、
心理的な優位が局面に影響を及ぼすことは実際にあります。
ただし、それはあくまで戦略・心理の変化による結果であり、
“見えない力”によって結果が左右されているわけではありません。
「流れを変える方法」はあるのか?
確率を操作することはできません。
しかし、自分の状態を整えることで結果に与える影響を減らすことは可能です。
- 焦ったら一旦離席する(休憩・リフレッシュ)
- 無理な勝負を控える(冷静さを保つ)
- データや確率に基づくプレイを意識する
これらは「悪い流れを断ち切る」最善の選択肢です。
まとめ
- 「流れ」は科学的に存在しないが、精神状態によって“あるように感じる”ことがある
- 勝ち負けの偏りは、確率的にも心理的にも起こり得る
- 感情に流されず、冷静な判断とデータに基づいた行動が最も重要
- 「流れ」は外的要因ではなく、自分の内面が生み出すもの
「今日はツイてない」と思ったときこそ、一歩引いて考えるチャンスです。
真に強いプレイヤーとは、「流れに頼らず、確率と心理を味方につける人」なのかもしれません。
「統計学」のマージャン戦術 (近代麻雀戦術シリーズ)
Amazonで見る