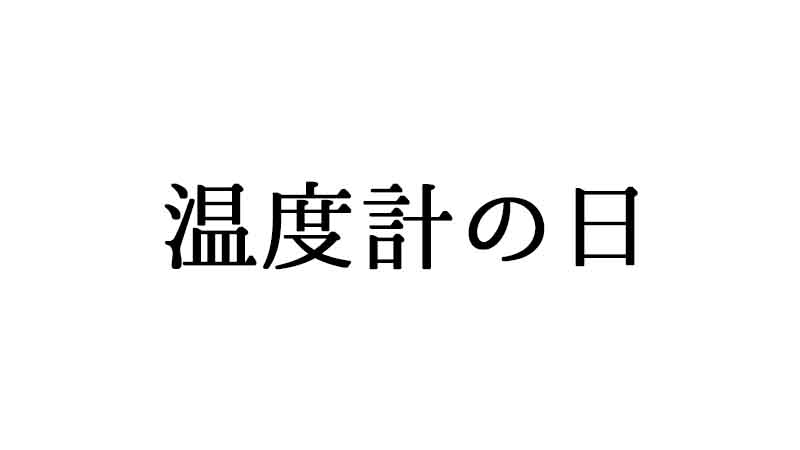5月14日は「温度計の日」。
「温度計なんて毎日見るけど、そんな記念日があるの?」
「なぜその日なの?誰が決めたの?」
そんな素朴な疑問を持ったあなたに、温度計の歴史と科学の面白さをギュッと3分でお届けします。
結論:温度計の日は“温度を測る技術”の進歩をたたえる日
- 由来:5月14日はガブリエル・ファーレンハイトの誕生日(1686年)
- 功績:水銀温度計の実用化と華氏(°F)スケールの考案
- 意義:温度計の科学的貢献を再認識し、理科教育・気象理解を促す
- 現状:公式な国の記念日ではないが、科学好きに人気の“トリビア記念日”
なぜ5月14日?ファーレンハイトとは何者?
この日は、ドイツ生まれの物理学者ガブリエル・ファーレンハイト(1686–1736)の誕生日に由来します。
- 1714年ごろ、水銀を使った安定的な温度計を開発
- 1724年、華氏温度スケール(°F)を発表
- 氷点:32°F
- 沸点:212°F
現在もアメリカではこの華氏スケールが広く使われています。
※「温度計が発明された日」ではなく、「発明者の誕生日」であることに注意しましょう。
温度計って、いつからあるの?
温度を測るという発想は古く、17世紀にはすでにアルコール式の温度計が存在していました。
ファーレンハイトはこれを改良し、水銀を使った高精度な温度計を開発。
これにより、医療・科学・気象などでの温度測定の信頼性が大きく向上しました。
その後、スウェーデンのセルシウスが摂氏スケール(℃)を考案し、現在の日本の標準となっています。
ちなみに「水は100度以上にはならないのか?」と思ったことがある方には、
「鍋は強火にしても100度以上ならないって本当?」もおすすめです。
温度計の種類と特徴
| 種類 | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 水銀温度計 | 医療・研究(旧式) | 高精度だが毒性のため現在は使用制限あり |
| アルコール温度計 | 冷蔵庫・気象観測など | 凍りにくく安価、赤や青色の液体が特徴 |
| 電子温度計 | 医療・家庭用 | 測定が速く、安全性が高い |
| 放射(赤外線)温度計 | 工業・食品・非接触計測 | 離れた場所からでも瞬時に温度が測れる |
現代では、水銀の毒性を避けるため、電子式やアルコール式が主流になっています。
気象観測ではどうやって温度を測っているの?
気象庁では、地表から約1.5mの高さにある「百葉箱」と呼ばれる通気性のある箱の中で気温を測定します。
- 設置場所は風通しの良い日陰
- 地面からの熱の影響を避けるため高さにも配慮
気温は、風や日射、地形などにも影響される繊細なデータ。
「強風が発生する仕組み」を理解することでも、温度の役割の重要性が見えてきます。
温度にまつわる豆知識
- 体温計の“振る”文化は水銀式の名残。今は電子式が主流。
- 水銀温度計の製造・輸入は2017年から原則禁止(水俣条約による規制)
- 華氏(°F)と摂氏(℃)の換算:
- 32°F = 0℃(氷点)
- 212°F = 100℃(沸点)
まとめ:温度計は“科学の見えない努力”の結晶
- 5月14日は「温度計の日」=ファーレンハイトの誕生日に由来
- 水銀温度計と華氏スケールは科学の飛躍に貢献
- 現代は電子式やアルコール式が主流
- 温度は医療・気象・生活あらゆる分野で重要な役割を持つ
普段は気にも留めない「温度」や「体温」ですが、
そこには数百年にわたる研究者たちの知恵と工夫が詰まっています。
5月14日、少しだけ“温度を測る”という行為に思いを巡らせてみませんか?