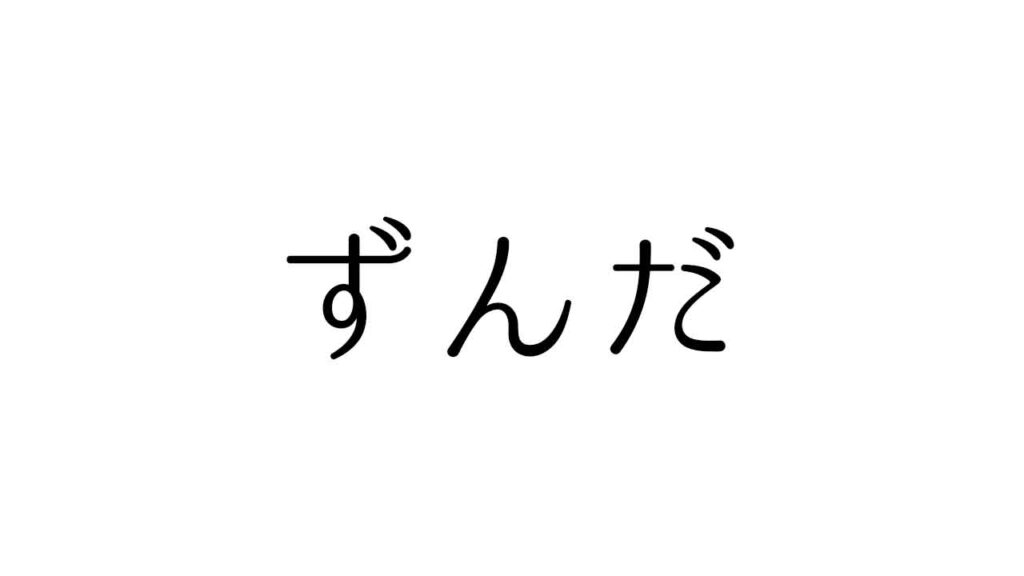ずんだ餅やずんだシェイクなどで知られる「ずんだ」。その鮮やかな緑色と独特の風味は、宮城県を中心とした東北地方の味として全国的にも親しまれています。
でもふと気になりませんか?
「そもそも“ずんだ”って何語?誰が名付けたの?」
この記事では、そんなずんだの名前の由来や歴史、いつから食べられてきたのかを、複数の説とともに詳しくご紹介します。
「ずんだ」って何?どんな食べ物?
ずんだとは、枝豆をすりつぶして甘く味付けしたペースト状の食品。
「ずんだ餅」は、そのずんだをお餅にからめたもので、宮城県をはじめ東北地方で古くから親しまれてきた郷土料理です。最近では「ずんだシェイク」や「ずんだアイス」など、洋風スイーツとしても人気が高まっています。
「ずんだ」の名前の由来には諸説ある
1. 「豆を打つ(豆打=ずだ)」がなまった説
枝豆をすりつぶす=豆を打つ=豆打(ずだ)
これが訛って「ずんだ」になったとされる説です。
実際、昔は木槌やすりこぎで枝豆を砕き、餅にからめていたことから、この説には調理文化的な裏付けがあります。
2. 伊達政宗の「陣太刀」説
戦国武将・伊達政宗が戦の陣中で太刀を使って枝豆をすりつぶし、餅にのせて食べたという逸話があります。
その「陣太刀(じんだち)」がなまって「ずんだ」になった、という説です。
根拠は薄く伝説の域を出ませんが、仙台藩との結びつきが強い宮城県らしいエピソードとして今も語り継がれています。
3. 東北の方言に由来する説
宮城・山形など東北地方では「ずんだる(潰す・こねる)」という方言があります。
これがそのまま料理名になった可能性も指摘されています。
この説は言語学的にもっとも自然であり、複数の地域で共通語的に使われていたことからも有力とされています。
ずんだはいつからある?最古の記録と歴史
1697年の『本朝食鑑』に登場
江戸時代・元禄10年(1697年)に成立した『本朝食鑑(ほんちょうしょっかん)』には、枝豆をすりつぶして餅にからめる食べ方が記されています。
これは現代のずんだ餅とほぼ同じで、文献上確認できる最古の記録とされています。
江戸時代以降は行事食として定着
ずんだ餅は、お盆や正月などの節目に家庭で作られ、地域の特別な料理として根付いてきました。甘さ控えめで素材の味を活かす東北らしい味つけも特徴です。
ずんだを最初に考えたのは誰?
はっきりとした発案者の記録は残っていません。
しかし、東北地方の農村で自然発生的に広まったとされており、「郷土料理=集団的な知恵と文化の蓄積」と考えるのが妥当です。
とはいえ、伊達政宗との伝説的な関係や「陣太刀説」のような物語が残されているのも、ずんだという文化に厚みを与えています。
現代のずんだブームとスイーツ展開
ずんだのアレンジ商品も多数
- ずんだシェイク:仙台駅名物。枝豆の香りとクリーミーな甘さが人気
- ずんだアイス:ミルキーな中に塩味のきいた枝豆の風味が絶妙
- ずんだロールケーキ・まんじゅう:伝統と洋菓子の融合
ずんだは“伝統”という枠を越えて、現代のスイーツ文化にも柔軟に溶け込んでいます。
ちなみに、「きびだんご」のように地域の言い伝えや伝説に支えられた名物もあります。
「桃太郎」との結びつきが強い岡山名物については、こちらの記事で詳しく解説しています:
→ きびだんごとは?起源・桃太郎との関係・岡山の名物になった理由を解説
まとめ
- 「ずんだ」の語源には複数の説があり、方言・調理法・伝説が絡み合っている
- 江戸時代の文献にも記録があり、長い歴史を持つ郷土料理
- 近年はスイーツやお土産として全国で人気
- 発祥ははっきりしないが、伊達政宗との説話も根強い
ずんだは、宮城県を代表する味として、そして日本の伝統的な“豆文化”の象徴として、今なお進化を続ける食文化です。
旅行やお取り寄せの際は、ぜひ本場の味に触れてみてください。