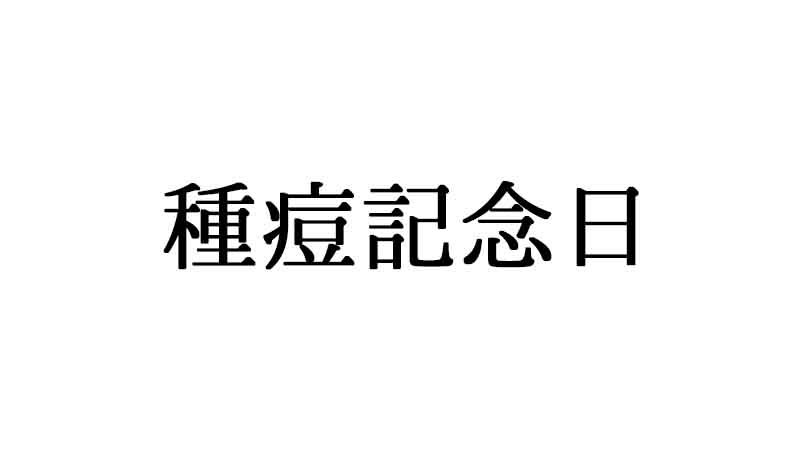「種痘記念日(しゅとうきねんび)」――
あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、実はこれは日本の医療史にとって極めて重要な一日です。
この記事では、種痘記念日の意味や由来、なぜ5月14日なのか、世界との違い、天然痘やワクチンの歴史までを、わかりやすく丁寧に解説します。
結論:種痘記念日は、日本でワクチン接種が始まった「医療の原点」を記念する日
- 日付:5月14日
- 読み方:「しゅとうきねんび」
- 意味:日本で初めて種痘(天然痘ワクチン)が成功した日を記念するもの
- 由来:1858年5月14日、蘭方医・伊東玄朴らが初の種痘に成功
なぜ5月14日?由来と歴史的背景
1858年5月14日、江戸時代の蘭学医・緒方洪庵の弟子である伊東玄朴らが、当時流行していた天然痘の予防接種(種痘)を日本で初めて成功させた日です。
この一歩は、感染症との長い戦いの中で日本医療の礎となりました。
その功績をたたえて、医療関係者を中心に「種痘記念日」として毎年語り継がれています。
誰が決めたの?公式な祝日ではないの?
種痘記念日は国民の祝日ではありませんが、公的機関や医療団体、教育現場などで、感染症対策の啓発の一環として定着しています。
正式な制定年は不明ですが、1970年代以降のワクチン普及や、1980年の天然痘根絶を契機に、医療教育や感染症の記録として広まりました。
世界でも祝われているの?
「種痘記念日」は日本独自の記念日です。
ただし、世界では1979年5月8日、WHO(世界保健機関)が「天然痘根絶」を公式に宣言したことが記念日的に扱われています。
| 国・機関 | 記念日 | 意味 |
|---|---|---|
| 日本 | 5月14日 | 初の種痘成功(1858年) |
| WHO(世界) | 5月8日(1979) | 天然痘の世界的根絶宣言 |
天然痘とは?どんな病気だったのか
天然痘(てんねんとう)は、かつて人類を苦しめた致死率30%超のウイルス性感染症。
- 発疹・高熱・皮膚に深刻な跡を残す
- 古代エジプトから中世ヨーロッパまで広範に流行
- 世界中で数億人が命を落としたとされる
種痘とは?そして誰が始めた?
種痘(しゅとう)は、牛痘ウイルスを使って天然痘を予防する接種法。
18世紀のイギリスの医師、エドワード・ジェンナーが1796年に実施したことが世界のワクチン史の始まりです。
- 牛痘にかかった人は天然痘にかからないという観察に基づく
- 世界初の「ワクチン」誕生の瞬間
- 200年をかけて、ついに天然痘を根絶
なぜ今、種痘記念日が大切なのか?
新型コロナやインフルエンザなど、感染症が再び身近な脅威になっている今こそ、
「ワクチンがどれだけ多くの命を救ってきたか」を思い出す機会が必要です。
実際に現代でも「インフルエンザは2回かかることもある?」といった感染症に関する知識が重要視されています。
また、「再生医療」など最先端医療が進む中、
過去の医療の歩みを知ることが“いま”の医療理解にもつながります。
まとめ:ワクチンの歴史を振り返る、大切な一日
- 5月14日は「種痘記念日」
- 日本で初めて天然痘ワクチン(種痘)が行われた日
- 世界では5月8日(天然痘根絶日)も重要な節目
- ワクチンの力で世界から消えた唯一の病気=天然痘
- 今だからこそ、過去の努力と知恵に目を向ける機会に
私たちの命を守ってきた「予防接種」の原点を、
この日だけでも静かに、そして深く見つめ直してみませんか?