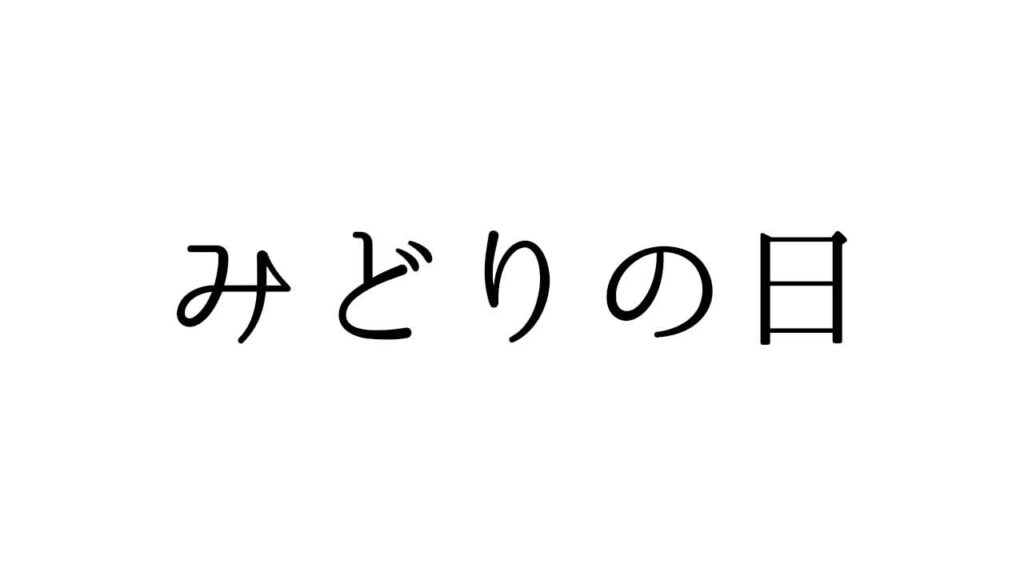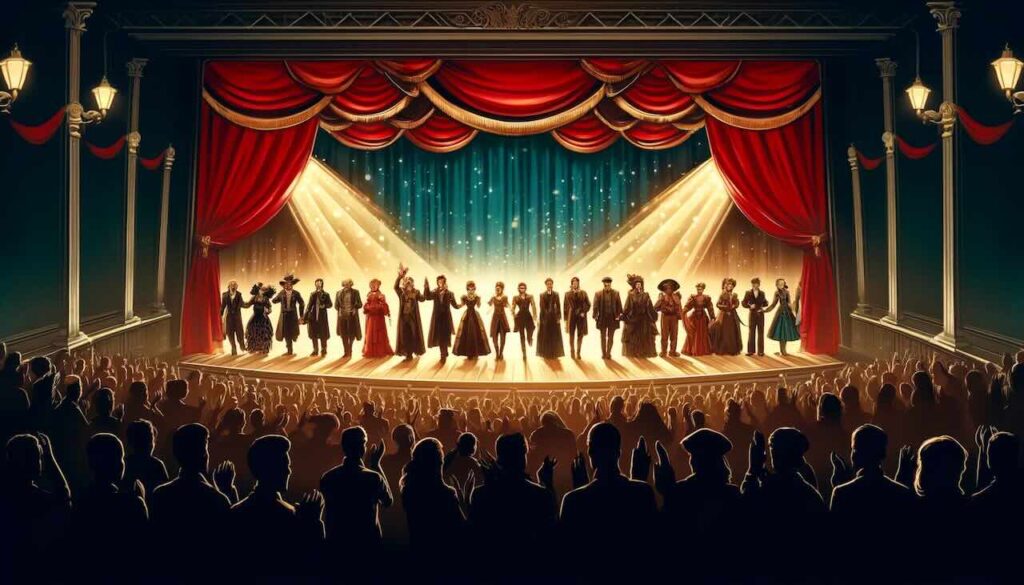ゴールデンウィークの中で、なんとなく過ごしてしまいがちな「みどりの日」。でも実はこの祝日、もともと昭和天皇の誕生日と深く関わっていることをご存じでしょうか?
この記事では、「みどりの日」の意味や成り立ち、なぜ5月4日なのか、そして昭和天皇との意外な関係まで、誰でもわかるように丁寧に解説します。
結論:みどりの日は昭和天皇の自然愛に由来する祝日
もともと4月29日だった「みどりの日」は、昭和天皇の自然への深い関心にちなんで生まれた祝日です。2007年に「昭和の日」と分離され、現在は5月4日に「自然に親しみ、その恩恵に感謝する日」として位置づけられています。
「みどりの日」はいつからあるの?
「みどりの日」が誕生したのは1989年。昭和天皇の崩御により、4月29日だった「天皇誕生日」は祝日のまま残すかどうか、政治的な議論が巻き起こりました。
結果として、「昭和天皇を個人として称えるのではなく、自然に親しんだお人柄に着目しよう」という意図で、「みどりの日」という名がつけられたのです。
当初は4月29日が「みどりの日」とされていましたが、2007年の法改正で5月4日に移動し、4月29日は新たに「昭和の日」として復活しました。
昭和天皇と「みどり」の意外な関係
昭和天皇は、実は生物学者としても知られています。とくに海洋生物や植物の分類研究に熱心で、研究論文も複数残しているほど。
その自然への深い愛情から、「自然に親しみ、その恩恵に感謝する日」という理念が、祝日として正式に定められたのです。
みどりという言葉は、自然や生命の象徴。日本の四季の豊かさを象徴する言葉でもあり、現代の気候変動や環境意識の高まりとも深く重なります。
なぜ5月4日になったのか?
かつて5月4日は「国民の休日」として定められていました。これは、祝日に挟まれた平日を自動的に休みにする制度によるもので、具体的には5月3日の「憲法記念日」と5月5日の「こどもの日」の間の日が対象でした。
2005年の法改正によって、これを単なる休日ではなく「意味ある祝日」として活用するために、「みどりの日」がこの日に移動されることになったのです。
こうして、昭和天皇の誕生日は「昭和の日」として4月29日に復活し、「みどりの日」は5月4日に生まれ変わりました。
現代における「みどりの日」の意味とは?
5月4日の「みどりの日」は、「自然とふれあい、感謝する日」という意味合いをもっています。
自然との関係を見直す機会として、公園や山に出かけたり、家庭菜園に取り組んだり、植樹活動を行ったりする人も増えています。
都市化や気候変動が進む現代では、身近な“みどり”とふれあうことの大切さが、よりいっそう高まっています。
実際に自然とふれあうヒントとしては、
- 公園や森林でのんびり過ごす
- 家庭菜園をはじめてみる
- 緑茶や和菓子を味わいながら季節を感じる
といった過ごし方もおすすめです。
「みどり」にちなんで、春の自然現象についてもっと知りたい方には、
春一番とは?意味・由来・観測条件をわかりやすく解説 や
春の嵐とは?なぜ春に嵐が多いのか原因と気候の変化をわかりやすく解説
といった記事もおすすめです。
「昭和の日」との関係性も忘れずに
「みどりの日」は昭和天皇に由来する祝日ですが、彼の誕生日であった4月29日は、今では「昭和の日」となっています。
この日は、昭和という激動の時代を振り返るための祝日として、「戦争と平和」「経済復興」「高度成長」などの歴史的な意義を再確認するために設けられたものです。
みどりの日と昭和の日、両者は兄弟のような関係でありながら、それぞれが独立した意味を持っている点がユニークです。
まとめ
- 「みどりの日」は1989年、昭和天皇の自然愛にちなんで誕生
- 2007年から5月4日に移動し、4月29日は「昭和の日」に再設定
- 現代では、自然との共生を意識する日としてますます重要に
- 自然を感じる行動が、みどりの日の本質にふさわしい過ごし方
- 昭和天皇の功績を背景に、時代の記憶と自然の未来を考える日
今年のみどりの日は、スマホを置いて、風の音や草木の匂いに耳を澄ませてみてください。あなたの心と自然が、少しだけ近づく一日になるかもしれません。
誰かに話したくなる 日本の祝日と歳事の由来
Amazonで見る