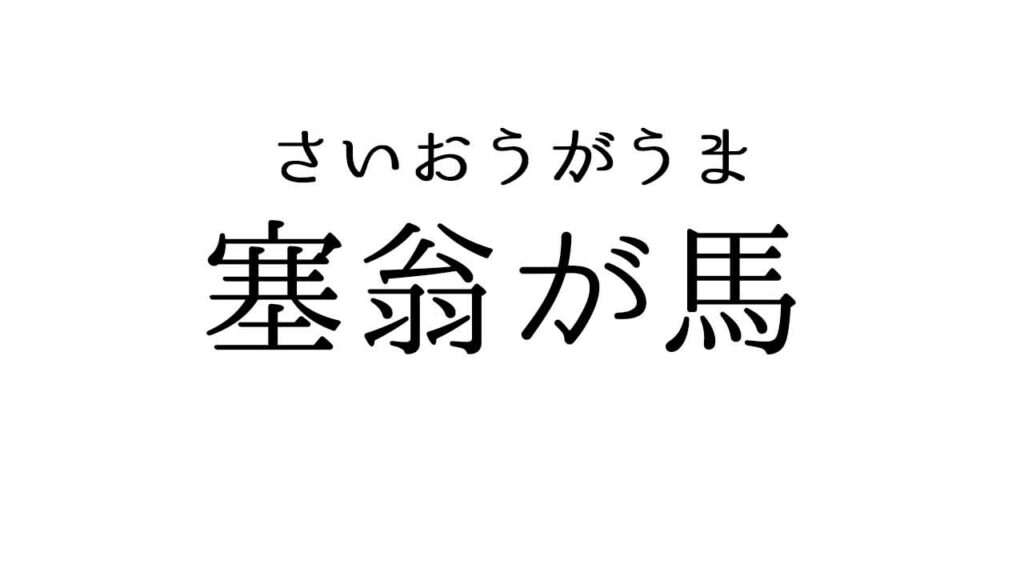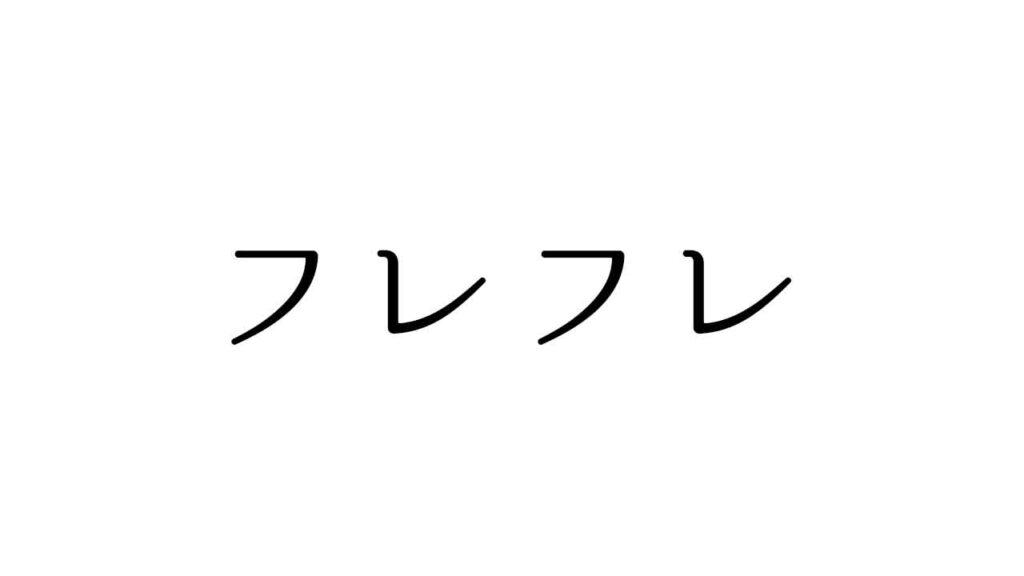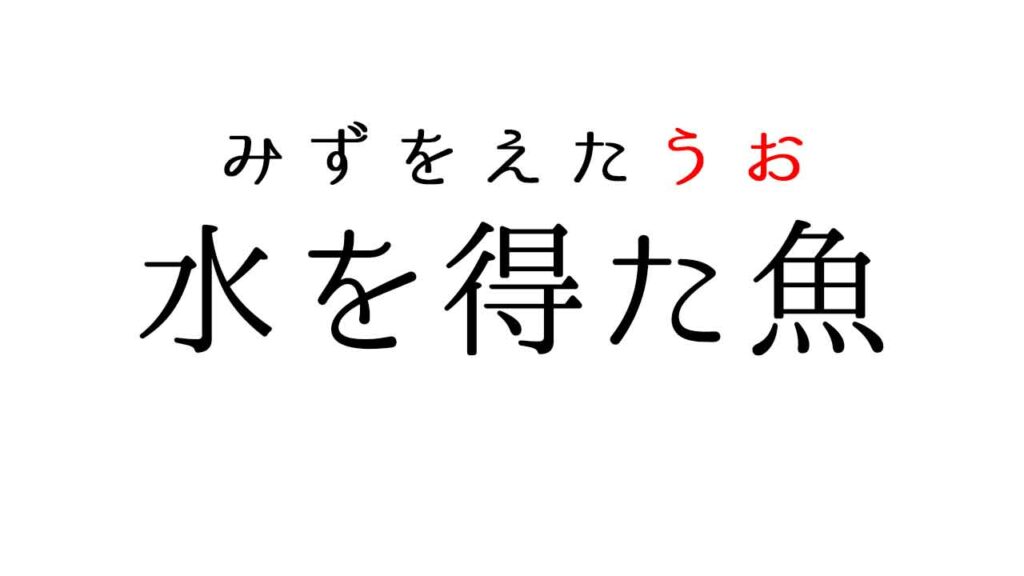人生、うまくいかないことばかり…でも、何が幸運で何が不運かは、後になってみないと分からないもの。
そんなときに思い出したいのが、「塞翁が馬(さいおうがうま)」という故事成語です。
結論:「幸不幸は予測できない」という教訓
この言葉が伝えたいのは、とてもシンプルな真理です。
「一見すると不幸に見えることが、後から幸運につながることがある。逆もまたしかり」
だからこそ、目の前の出来事に一喜一憂せず、長期的な視点で物事を見ましょうというメッセージが込められているのです。
物語の由来:中国古典『淮南子』の逸話
この言葉は、中国の古典『淮南子(えなんじ)』に登場する寓話に由来します。
国境の町に住む老人(塞翁)の馬が逃げてしまい、周囲が慰めに来たところ、老人は「これが不幸とは限らない」と言います。
すると後日、逃げた馬が立派な野馬を連れて戻ってきます。人々は今度は祝福に訪れますが、老人は「これが幸運とも限らない」と語ります。
その後、塞翁の息子が野馬に乗って落馬し足を折る不運に見舞われます。ところが戦争が起こり、健康な若者たちは徴兵され戦死する中、息子は足の怪我のおかげで戦争に行かず命が助かったのです。
この連続する出来事こそ、「塞翁が馬」の本質をよく表しています。
現代での使い方(具体例)
- 転職やリストラの場面
「リストラされたときはショックでしたが、新しい職場のほうが自分に合っていて活躍できています。まさに塞翁が馬ですね」 - 受験や進路選択の挫折
「第一志望の大学には落ちましたが、進学先で本当にやりたい分野に出会えました。結果的に良かったと思います。塞翁が馬ですね」 - 日常のささいなトラブルにも
「電車が遅れて予定をキャンセルしたけど、そのあと偶然出会った人との話が転機になった。塞翁が馬ってこういうことかも」
使用のポイント
- 一見不運に思える出来事が、結果的に良い方向に進んだとき
- 幸運だと思っていたことが、のちにトラブルの原因となったとき
- 今の状況を安易に良し悪しで判断せず、保留したいとき
「禍福は糾える縄の如し(かふくはあざなえるなわのごとし)」も同様に、善悪は絡み合って判断しにくいという思想を表すことわざです。
→ 「禍福は糾える縄の如し」はどういう意味?誰が言った?用例は?
関連する教訓や現代での応用
- 失敗や挫折の意味を“あとから”考える習慣
- 成功も慢心せず、変化への備えを忘れない姿勢
- 「今の困難も、いつか“転機”になるかもしれない」という柔軟な考え方
たとえば、昔取った杵柄ってどういう意味?そもそも杵柄って何? のように、過去の経験が後から生きることも、「塞翁が馬」の教えとつながっています。
まとめ:判断は“いま”ではなく“あと”でわかる
「塞翁が馬」は、人生の“予測不能さ”を教えてくれる言葉です。
目の前のことに振り回されすぎず、「この経験は、あとでどうつながるのだろう?」と一歩引いて考える習慣が、心の余裕や強さにつながります。
変化の多い現代社会こそ、この故事の教えが生きる時代。ふとした時に思い出して、自分の人生を俯瞰してみてください。
ちいかわ 慣用句&故事成語 (KCデラックス)
Amazonで見る