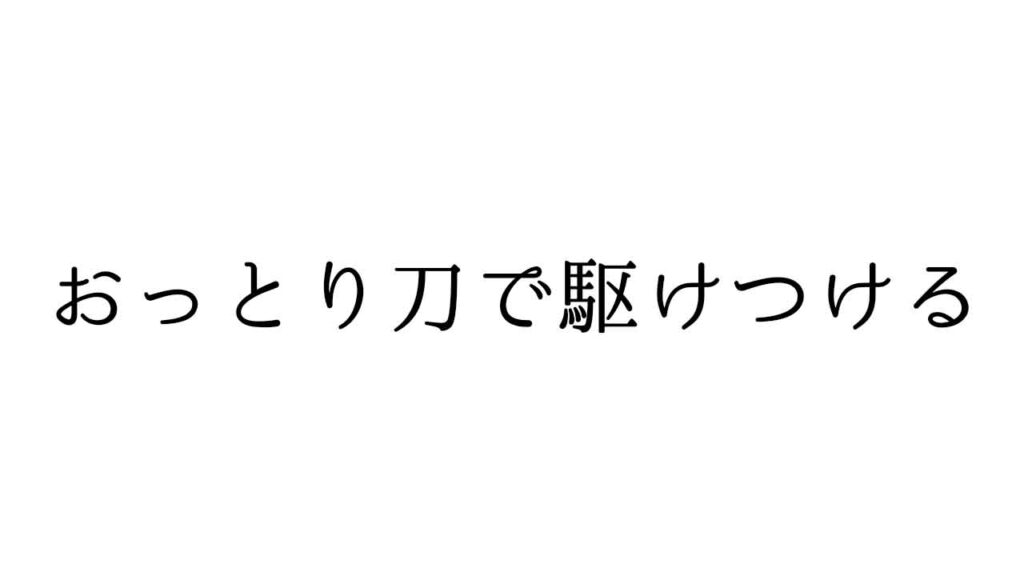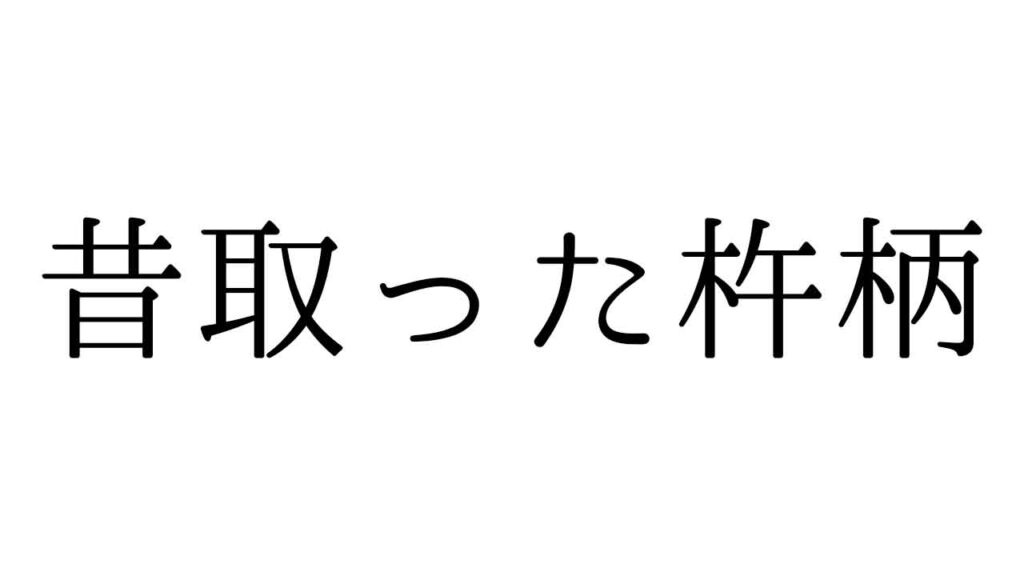「おっとり刀で駆けつける」という表現、耳にしたことはありますか?
一見すると「のんびりやってくる」ように感じられますが、実はこの言葉、まったく逆の意味を持つのです。
この記事では、「おっとり刀」の語源や歴史、現代での使い方まで、スッキリ理解できるよう解説します。
結論:「おっとり刀で駆けつける」は“すぐに駆けつける”という意味
まず覚えておきたいのは、「おっとり刀で駆けつける」は「慌てて急いで向かう様子」を表す言い回しだということです。
「おっとり=おっとりした性格」と勘違いしがちですが、この場合の「おっとり」はまったく別物。
語源をたどると、武士の文化に深く根ざした言葉であることがわかります。
「おっとり刀」の本来の意味とは?
「おっとり刀」は、漢字では「押っ取り刀」と書きます。
これは刀を鞘から抜く間もなく、とにかく駆けつける様子を表した言葉です。つまり――
- 緊急事態に刀を抜く暇すらなく駆け出す
- 一刻を争う場面でとる行動
というイメージです。
実際、江戸時代の武士社会では、「刀を腰に差したまま急ぐ=非常に急を要する行動」という意味合いを持っていたとされます。
このような文化背景は、「刀剣や武士の歴史」に詳しい記事でも紹介しています →
👉 居合道の由来と発展、日本の武道としての成り立ち
どんな時に使う?現代での具体例
現代では刀を持つことはありませんが、比喩表現として、次のような場面で使われます。
- 緊急対応時の行動描写に
- 「取引先からトラブルの連絡が入り、おっとり刀で現場に向かった」
- 「上司に急に呼ばれて、おっとり刀で会議室へ駆け込んだ」
- 家族・友人など、個人的な緊急時に
- 「友人が倒れたと聞き、おっとり刀で病院に駆けつけた」
- 「地震速報が流れ、おっとり刀で家族のもとへ走った」
要するに「慌ててすぐ行動に移す場面」で使われるのが特徴です。
「おっとり刀」の語源と背景にある武士文化
「おっとり」は「押し取る」から転じたもので、「急いで手に取る」「そのまま駆け出す」という意味がもともとの語源です。
この背景を理解するうえでは、日本の武士社会にも触れておくとより深く味わえます。
類似表現や混同しやすい言葉に注意
「おっとり刀」は「おっとりした性格」などの“のんびり”という意味とは完全に異なる言葉です。
このように、現代の感覚と語源の意味がずれる言葉は少なくありません。
他にも語源を知ると印象が変わる言葉には、以下のようなものがあります:
- 「敷居が高い」(本来は“行きづらい”という意味)
- 「役不足」(“自分には簡単すぎる役”という意味)
これらの言葉も混同しやすいので、ぜひ別の記事でチェックしてみてください。
まとめ
- 「おっとり刀で駆けつける」は、“すぐに駆けつける”という意味
- 語源は武士が刀を抜く暇もなく駆け出す姿に由来
- 現代では緊急時や慌てて向かう様子を表す比喩表現として使われる
- 「おっとり=のんびり」ではなく、全く別の成り立ちであることに注意
言葉の意味や背景を知ることで、日常の言い回しがぐっと奥深く感じられるものです。
小学生のまんが慣用句辞典 改訂版
Amazonで見る