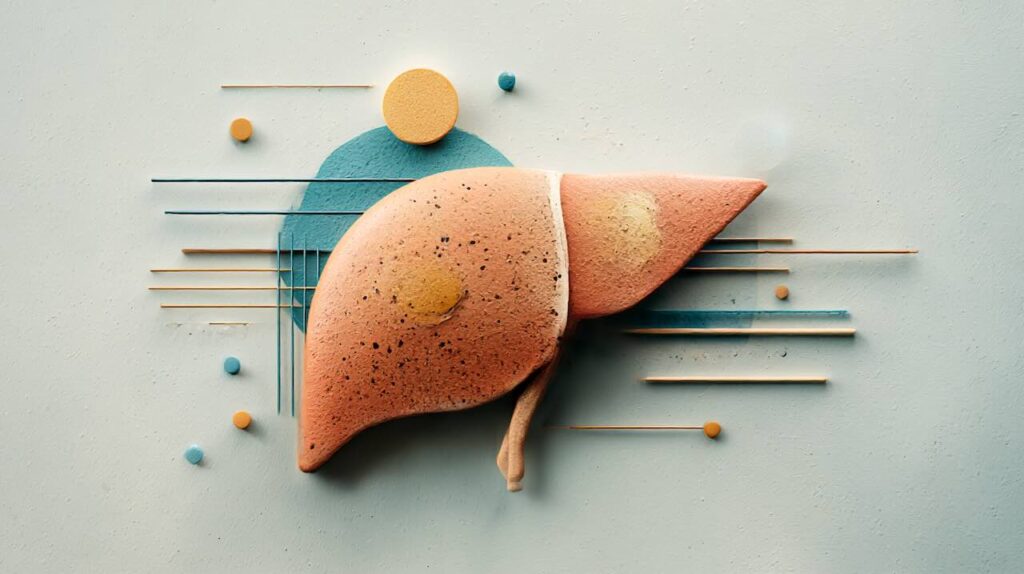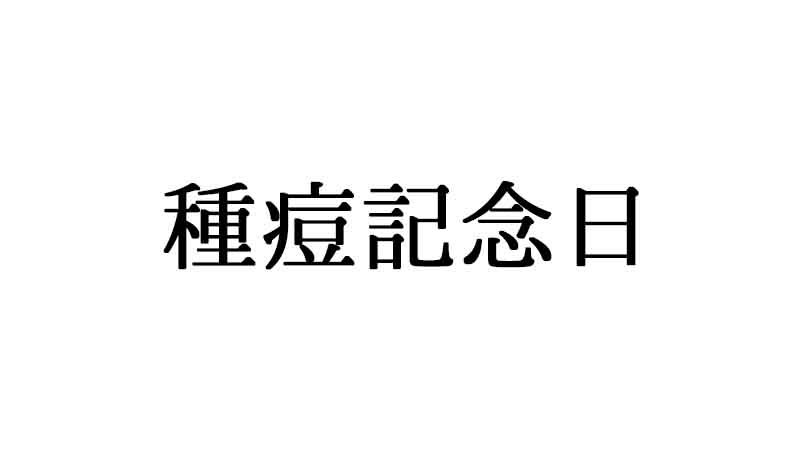「今日は看護の日です」と言われても、「なんで5月12日なの?」「国際看護師の日と違うの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実はこの日、看護という仕事に携わるすべての人にとって大切な意味があるだけでなく、日本独自の背景も存在します。
ここでは、5月12日が「看護の日」になった理由、世界と日本での違い、そして私たちにできることをわかりやすくご紹介します。
5月12日はナイチンゲールの誕生日
5月12日は「近代看護の母」と称されるフローレンス・ナイチンゲールの誕生日(1820年)です。
彼女はクリミア戦争で衛生環境を改善し、負傷兵の死亡率を劇的に下げました。統計や衛生学の知見を用いた彼女の看護は、のちの医療制度の礎となったのです。
この偉業を称えて、世界中で「看護師」に感謝する日が5月12日となりました。
「国際看護師の日」と「看護の日」の違い
| 項目 | 国際看護師の日 | 看護の日(日本) |
|---|---|---|
| 制定 | 1974年(ICN) | 1990年(厚生労働省) |
| 主体 | 国際看護師協会(ICN) | 日本政府・日本看護協会 |
| 目的 | 世界中の看護職の功績を称える | 国民に看護の重要性を伝える |
「国際看護師の日」は世界共通の記念日であり、日本の「看護の日」はより啓発活動に重点を置いた取り組みです。
なぜ日本では「看護の日」が必要だったのか
1990年、当時の首相・海部俊樹氏が少子高齢化の進行を受け、「看護の役割と重要性を社会全体で認識すべき」としてこの記念日を設けました。
翌1991年から本格的に普及啓発活動が始まりました。
このような背景から、日本の「看護の日」は単なる感謝の場ではなく、社会全体で看護を学び、支える意識を高める日でもあるのです。
同じく5月中旬には「医師の日」もあり、クラシコ・医師の日とは?5月14日との関係を解説も併せて読むと、医療全体への理解が深まります。
看護週間ってなに?
5月12日を中心に、前後1週間を「看護週間」と定めています。
この期間には以下のような活動が行われています:
- 看護体験セミナー
- 地域との交流イベント
- 医療現場の紹介やパネル展示
これにより、普段触れる機会の少ない看護の現場や、医療従事者の思いを知る機会が広がっています。
よくある疑問と答え
Q. 看護の日は祝日?
→ いいえ、祝日ではありません。あくまで記念日として定められた日です。
Q. 日本だけ?
→ 「看護の日」は日本独自ですが、5月12日は世界中で「国際看護師の日」として広く認識されています。
Q. 看護師さんに何かできることは?
→ 「ありがとう」の一言、SNSでのメッセージ、子どもと看護について話すことでも十分意味があります。
私たちにできること
5月12日は、「ありがとう」と言えるチャンスです。
病院や介護施設で働く方だけでなく、地域で人を支えている全ての“看護の心”に敬意を伝えましょう。
また、現代医療の進化にも興味がある方は、再生医療とは?従来医療との違いやメリット・課題をやさしく解説も読んでみてください。
まとめ
- 5月12日はナイチンゲールの誕生日
- 「国際看護師の日」と「日本の看護の日」は別物
- 日本では1990年に制定、1991年から実施
- 看護週間を通じて、看護の理解と関心を広げる期間
- 医療現場を支える全ての人に、感謝の気持ちを伝えるきっかけに
誰かを支える力が、社会を支える力につながっていきます。
今日という日を通して、私たち一人ひとりがその輪の一部になれたら素敵ですね。
ナイチンゲール: 戦場を、きぼうの光でてらした「天使」
Amazonで見る