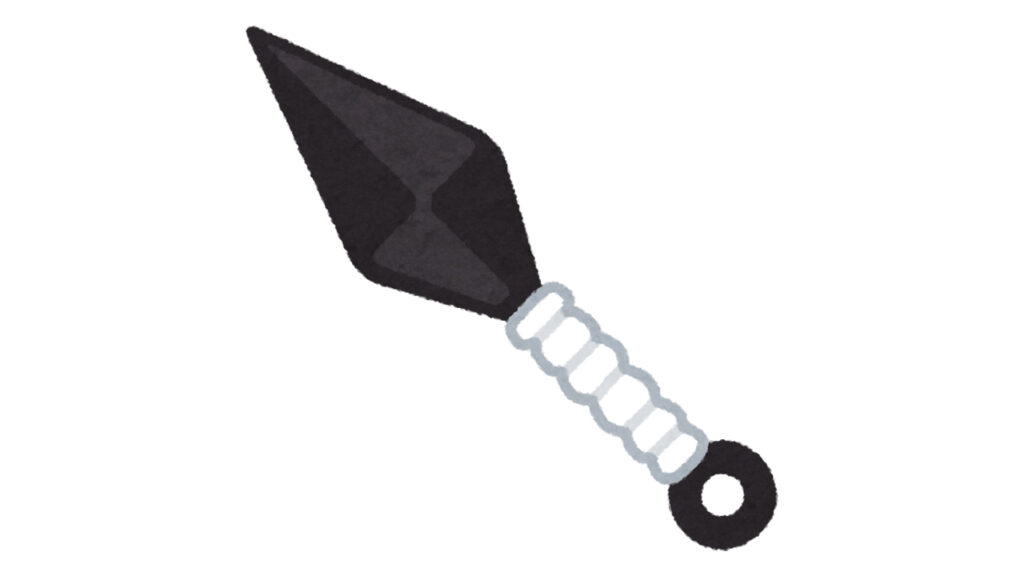「クナイって忍者が使ってた武器だよね。でもあれって本当に実在したの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?アニメや映画でよく登場するクナイは、実際には農具から生まれたという説があります。
この記事では、クナイの起源や歴史、誰が作ったのか、どうやって作られていたのか、さらに忍者との関係についても詳しく解説します。
結論:クナイはもともと農具がルーツで、後に忍者が改良し武器として使用した道具です。
クナイの起源は農具だった?
クナイの起源は、鎌倉時代(1185年〜1333年)に使われていた「土佐クナイ」と呼ばれる農具・工具にあると考えられています。土佐国(現在の高知県)で使用されていたこの道具は、小型のツルハシや鏨(たがね)に似た形状で、硬い土を掘ったり木を削ったりする多目的ツールでした。
武器として作られたものではなく、携帯性と頑丈さを兼ね備えた実用的な工具だったのです。
忍者がクナイを武器に変えた背景
戦国時代(1467年〜1615年)になると、伊賀や甲賀などの忍者たちは、こうした農具を戦闘にも使えるよう改良し始めました。中でも伊賀流忍術の祖とされる**藤林長門守(ふじばやしながとのかみ)**は、クナイの形状や重量を調整し、隠し持ちやすく、投げやすくしたと言われています。
クナイは、
- 投げて敵をけん制する
- 壁に突き刺して登る足場に使う
- 扉の鍵をこじ開ける といった多目的なツール兼武器として、忍者の活動に欠かせない存在となりました。
クナイの作り方:古来の鍛冶技術
古来のクナイは、鉄を鍛造して一つひとつ手作業で作られていました。作成工程は以下の通りです:
- 鉄の棒を高温で熱する
- ハンマーで叩いて延ばす
- 先端を尖らせる
- 柄の部分に穴を開けて紐が通せるようにする
- 表面を研磨して完成
※この穴は「ヒモ通し穴」と呼ばれ、紐をつけて持ち運んだり、腰にぶら下げたり、他の道具と組み合わせるための工夫でした。
現代では、コスプレや演武用にステンレスやゴム製のクナイも流通しています。
クナイの種類と使い分け
クナイには主に2つの種類があります。
- 直刃クナイ
- 刃が直線的
- 主に投げ用
- 湾刃クナイ
- 刃が曲線的
- 近接戦闘に向いている
また、サイズも大小様々で、持ち運びや用途に応じて選ばれていました。
まとめ
クナイは日本の忍者文化を象徴する道具のひとつですが、そのルーツは意外にも農具にあります。土佐クナイのような実用工具が忍者によって改良され、戦闘や諜報活動にも活用されたのです。
鍛冶技術の高さ、道具の応用力、忍者の知恵が融合したクナイは、日本の歴史と文化を学ぶうえでも非常に興味深い存在です。
しのびや.com ゴム苦無 忍者 クナイ 本格的なのに柔らかく安全 (黒)
Amazonで見る