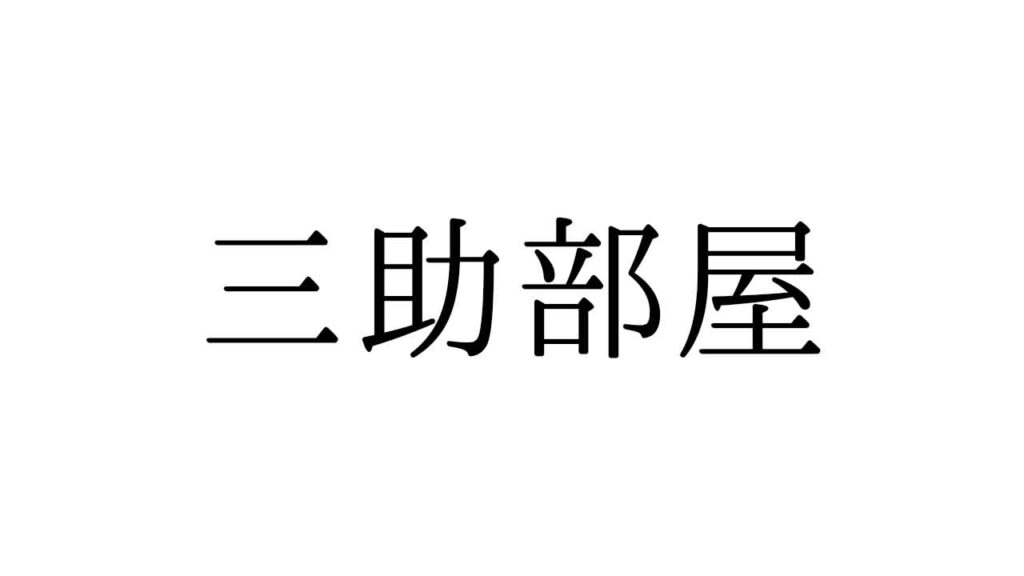銭湯に関する話題でよく出てくる「三助(さんすけ)」や「三助部屋(さんすけべや)」。でも実際に見たことがある人は少ないのではないでしょうか?
三助とは、かつての銭湯で欠かせなかった職業であり、その存在は江戸時代から昭和期まで続いていました。この記事では、三助と三助部屋の意味や歴史、現代への影響までを詳しく解説します。
結論:三助は江戸時代から続く銭湯の裏方として活躍した職人であり、現代の垢すり・マッサージ文化にその技術が受け継がれている
三助とは、かつて銭湯でお客の身体を洗ったり、湯加減の調整や清掃を担っていた男性職人。三助部屋は、その三助の控室や作業場であり、昭和中期までは多くの銭湯に存在していました。現在は姿を消しましたが、垢すりやマッサージといったサービスのルーツはここにあります。
三助部屋とは何か?
三助部屋とは、銭湯において三助が着替えたり、休憩したり、道具を管理したりするためのスペースです。規模や設備は銭湯ごとに異なりましたが、多くは浴室の裏手や奥に設けられていました。
三助部屋には、垢すり用のタオル、洗面器、石けんなどの道具が置かれ、まさに三助の仕事を支える拠点でした。
三助とはどんな仕事?
三助の語源には諸説ありますが、もっとも有力なのは「三つの助けをする者」という意味です。具体的には以下の3つの仕事を担当していました。
- 湯加減の調整
- 湯釜の火加減を見て、温度が熱すぎたりぬるすぎたりしないように管理。
- 浴場の清掃
- 営業前後や合間に、浴場全体を清掃して衛生状態を保つ。
- 利用者の体を洗う・垢すりをする
- お客の背中を流す、垢をこする、肩を揉むといったサービスを提供。
現代の感覚でいえば、公衆浴場専属の垢すり職人兼設備管理人といった立ち位置です。
三助のルーツと最盛期
三助という言葉は、江戸時代中期から使われ始めました。当時、銭湯の人気とともに来客が増え、単にお湯を提供するだけでなく、より快適なサービスが求められるようになりました。そうした中で生まれたのが三助です。
明治・大正・昭和初期にかけては、銭湯の数も増加し、三助の需要も高まりました。特に「混浴」が当たり前だった時代には、三助が仲介役として秩序を保つ存在でもあったのです。
当時の混浴文化や銭湯の歴史については、
銭湯はいつからある?混浴が当たり前だった時代と日本独自の銭湯文化の進化
で詳しく解説しています。
三助の消滅とその理由
昭和後期になると、以下のような変化が三助の役割を少しずつ奪っていきました。
- 銭湯利用者の減少(家庭風呂の普及)
- セルフサービス志向の強まり
- 衛生・プライバシーの観点からの敬遠
- 男女別浴の定着
結果として、三助は徐々に姿を消していき、三助部屋も必要とされなくなっていきました。
三助の仕事はどこに引き継がれた?
三助の「垢すり」「揉みほぐし」といった技術は、現代のマッサージ業やスパ施設、韓国式垢すりに受け継がれています。
特にスーパー銭湯や温泉旅館では、以下のようなサービスが提供されており、三助の文化がアレンジされて再生しているとも言えます。
- アカスリ
- タイ式マッサージ
- エステ・リラクゼーションサービス
銭湯文化と三助の関係を温泉文化から見てみる
実は日本の銭湯と温泉文化は密接に関係しています。どちらも「入浴を通じて体を癒し、人と交流する場」として発展してきました。
日本の温泉文化が世界とどう違うのかは、
温泉文化は日本だけのもの?世界各国の温泉事情とその違い
を読めば、より深く理解できます。
たとえば、草津温泉の「湯もみ」や共同浴場の文化も、三助がいた時代の銭湯と通じるものがあります。
草津温泉の成り立ちや効能については、
草津温泉の歴史・名前の由来・効能とは?いつから続く名湯かを3分で解説
を参考にしてみてください。
まとめ:三助は「人と風呂をつなぐ職人」だった
三助という存在は、単なる裏方ではなく、銭湯文化を支える重要な要素でした。
現在では職業としては消えつつありますが、その精神や技術は、現代の入浴文化の中に確かに生きています。三助部屋という言葉が消えても、「人の手で癒す」文化は決してなくなってはいないのです。
現代の銭湯や温泉で垢すりやマッサージを受けるとき、かつての三助に思いを馳せてみるのも一興かもしれません。
銭湯図解
Amazonで見る