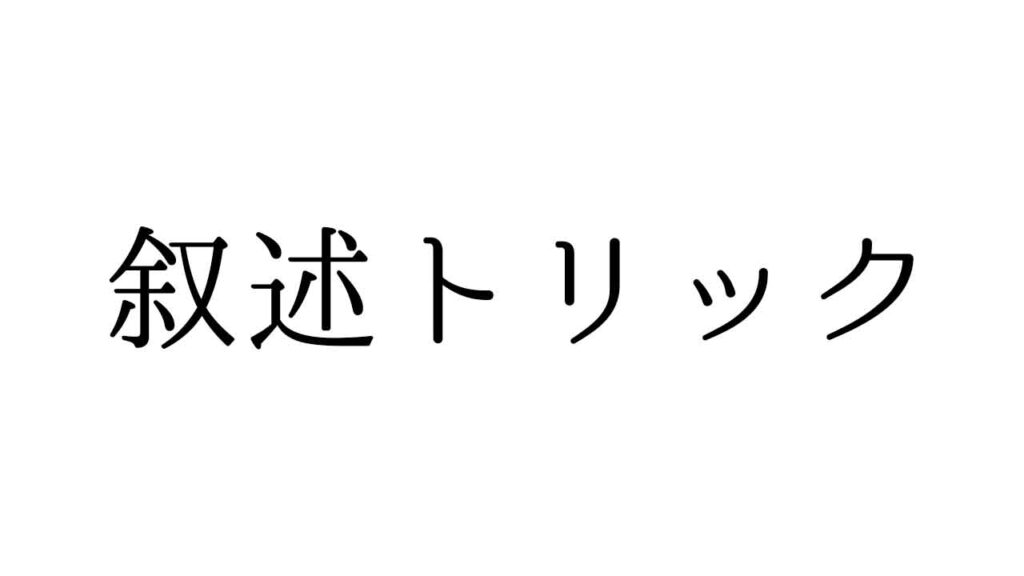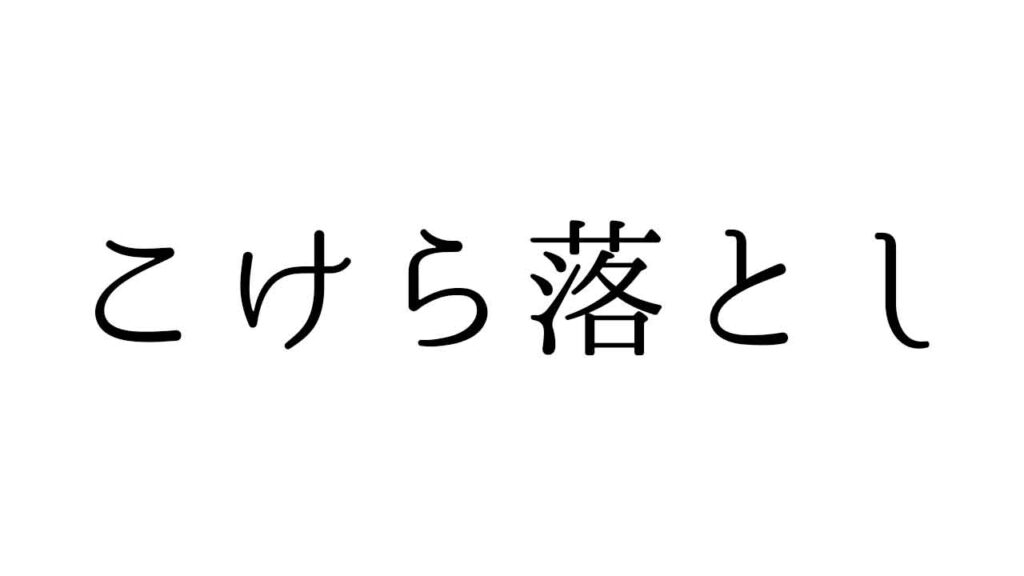「えっ、そんな真相だったの!?」
ミステリー小説を読んでいて、思わず読み返したくなるような驚き。
その正体が、「叙述トリック」と呼ばれる文章構造の仕掛けです。
この記事では、「叙述トリックとは何か?」という基本から、定番の使い方、読者を騙すテクニックのパターン、見破るためのヒントまで、わかりやすく解説します。
結論:叙述トリックとは「文章表現を使った錯覚の仕掛け」
叙述トリックとは、文章の書き方や言葉の選び方を工夫することで、読者に誤解させる技法です。
推理小説やミステリー作品でよく使われ、真相が明かされたときに「確かに書かれていたけど、思い込んでいた!」という驚きと納得が味わえる仕組みです。
視点の制限、時系列のずらし、あいまいな言葉の使い方などが主なテクニックです。
どうやって読者を「騙す」のか?
例えば、こんな一文を見てみましょう。
「その日、私は彼が最後に入った部屋を確認した」
多くの読者は、「彼が生きていたときに入った最後の部屋」と解釈しますが、
実は「彼の死体が運ばれた最後の部屋」だったかもしれません。
このように、自然な想像を利用して事実を隠すのが叙述トリックの核心です。
叙述トリックの4つの定番パターン
- あいまいな表現を使う
- 例:「山田さんは教室で倒れていた」
- → 実際は「別の場所で倒れた山田さんが、あとから教室に運ばれていた」
- 視点で情報を制限する
- 例:「私は窓から通りを見たが、誰もいなかった」
- → 実際は、通りの一部しか見えていなかっただけかもしれない
- 時系列を操作する
- 例:「昨夜8時のニュースを見ていたとき、物音がした」
- → 実は録画を見ていただけで、8時には現場にいた可能性もある
- 言葉の多義性を利用する
- 例:「彼は妻の写真を見ながら涙を流した」
- → 亡き妻を想う涙と思わせて、実はこれから殺す後悔の涙だった…という真相も
よくある仕掛けの例
- 語り手が実は犯人だった
- 一人の人物だと思っていたら双子だった
- 子供や老人だと思わせて実は別の人物だった
- 回想だと思っていた場面が現在進行形だった
こうしたトリックは、真相を知った後にもう一度読み返すと伏線に気づけて、物語の完成度の高さを実感できます。
叙述トリックの見破り方はある?
完璧に見破るのは難しいですが、以下の点を意識することで引っかかりにくくなります。
- 不自然な言い回し、妙にあいまいな表現に注目する
- 語り手の視点や情報の偏りを疑う
- 時間の説明や出来事の順序に違和感がないか確認する
- 「事実」と「想像」の境目を明確に意識する
ただし、叙述トリックは「読者を騙すこと」が目的ではなく、「騙されたことに納得できる構成」にこそ価値があります。
関連作品の魅力にも注目
叙述トリックが巧みに使われている作品は数多くありますが、たとえば『モンテ・クリスト伯』のような復讐劇にも、視点や時系列のズレを活かした構成があり、読み返すたびに発見があります。
詳しくは『モンテ・クリスト伯』とは?どんな話?復讐と正義を描いた名作小説をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。
まとめ
叙述トリックは、文章の巧みな構成によって読者の思い込みを利用する表現技法です。
ミステリーを読む醍醐味のひとつでもあり、「だまされた!」という快感と、「なるほど」と納得できる仕掛けが魅力です。
次に読むミステリーでは、ぜひ叙述トリックにも注目してみてください。読む力がぐんと鍛えられますよ。
叙述トリック短編集 (講談社タイガ)
Amazonで見る