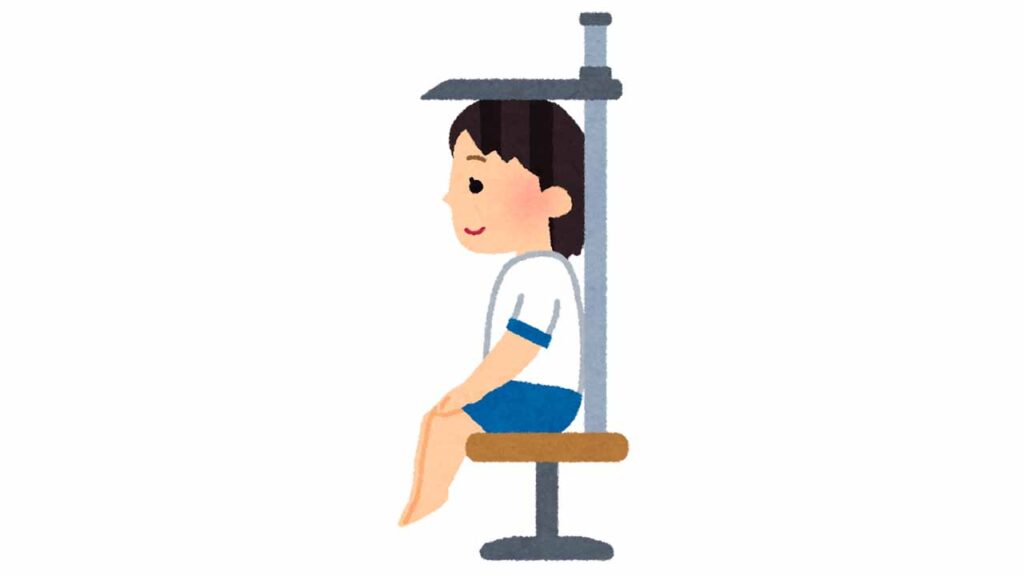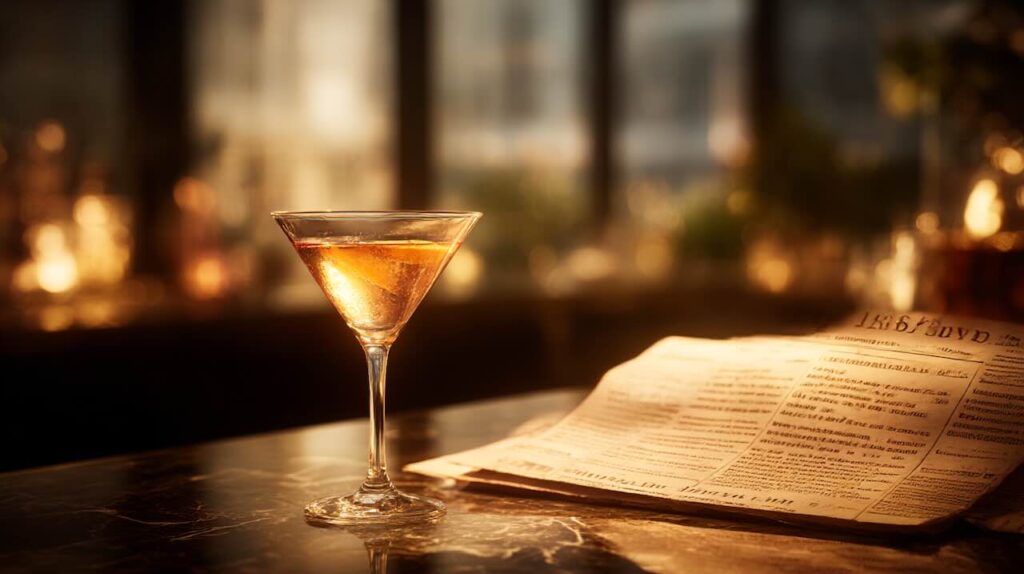「そういえば、昔は身体測定で“座高”も測ってたな…」
そんな記憶がある方も多いのではないでしょうか。
今回は、かつて当たり前だった「座高測定」について、その誕生から廃止に至るまでの歴史と背景を、
学校教育や健康観の変遷とともに、わかりやすくひもといていきます。
結論:座高は明治時代の徴兵目的で導入され、2016年に廃止された
座高測定は、もともとは健康のためではなく、徴兵制度と深く関係した軍事目的の検査でした。
その後、「健康管理」へと目的を変えながら続いてきましたが、科学的根拠の乏しさと実用性の低さから、現在では廃止されています。
明治時代:座高は「兵士に向いている体かどうか」を測る指標だった
日本で座高が測られるようになったのは明治11年(1878年)。
徴兵のための「活力検査」の一環として始まりました。
当時の価値観では、
- 足が短くて胴が長い=重心が低くて安定している
- =戦場で有利=理想の兵士
という考えがあり、「座高の高さ」=「兵士向きの体格」とされていたのです。
戦後は「健康指標」として定着
戦後、徴兵制度は廃止される一方で、座高測定は健康管理のための指標として学校で行われるようになりました。
昭和12年(1937年)の身体検査規定ではこう記されています:
「重要臓器の多くは体幹に集中しており、その発育状態こそが健康のバロメーターである」
つまり、「胴が長い=臓器がしっかり発達=健康」とする理論が広く信じられていたのです。
当時の学校では、身長・体重・視力・聴力に加えて、座高やBCG接種(はんこ注射)なども含め、
成長や健康を見守るための定期的な検査が実施されていました。
👉 BCG(はんこ注射)とは?結核予防のしくみ・効果・副反応までわかりやすく解説
座高測定の目的は何だったのか?
かつて文部科学省が示していた座高測定の主な目的は次の3つです:
- 個人や集団の体型・成長の変化を知る
- 胴体(内臓部)の発育状態を見る
- 統計的データを通じて集団傾向を把握する
とはいえ、これらの情報は身長・体重・肥満度などでも代替可能であり、
「座高でなければ測れない」という決定的な理由にはなっていませんでした。
教育現場の声:測る意味がわからない?
長年教職についていた私自身も、現場では次のような声を何度も耳にしました。
- 「測る意味がはっきりしない」
- 「健康との相関性が不明」
- 「結果をどう使えばいいのかわからない」
養護教諭の先生に聞いても、明確な答えが返ってくることはまれで、
「慣習として残っているだけ」という印象を持ったことをよく覚えています。
ついに2016年、座高測定は正式に廃止
文部科学省は2014年に学校保健安全法施行規則を改正。
2016年度から座高は必須測定項目から除外されました。
主な廃止理由
- 科学的根拠が乏しい
- 教育現場で活用されていない
- 成長評価には他のデータで十分対応できる
- 測定簡素化・合理化の流れ
まさに「形式だけの検査を続ける意味はない」とする現場の声が反映された結果といえるでしょう。
意外と根強かった「継続支持」の声
廃止当初、文部科学省の調査によると、
- 「省略してもよい」と回答した教職員は
- 小学校:28.3%
- 中学校:32.6%
- 高校:36.6%
つまり、半数以上の教員が座高測定の継続に肯定的だったのです。
長年行われてきた身体測定の一環としての慣れや安心感が、合理性よりも優先されていた現実がうかがえます。
まとめ:教育に必要なのは「なぜ?」と問い続ける姿勢
座高測定の歴史は、教育現場が時代や価値観と密接につながっていることを物語っています。
- 明治時代:徴兵のための数値管理
- 戦後〜平成:健康評価として継続
- 現代:実用性の欠如から廃止へ
そしてこの変遷が示しているのは、「慣習にとらわれず、本当に必要かを問い直す姿勢」が
教育においていかに大切か、ということです。
かつてのBCGや座高測定のように、「当たり前だったこと」がいつの間にか見直されていく今、
子どもたちにとって本当に必要な教育とは何かを、私たち大人自身が問い続けなければなりません。
学校のふしぎ なぜ? どうして?
Amazonで見る