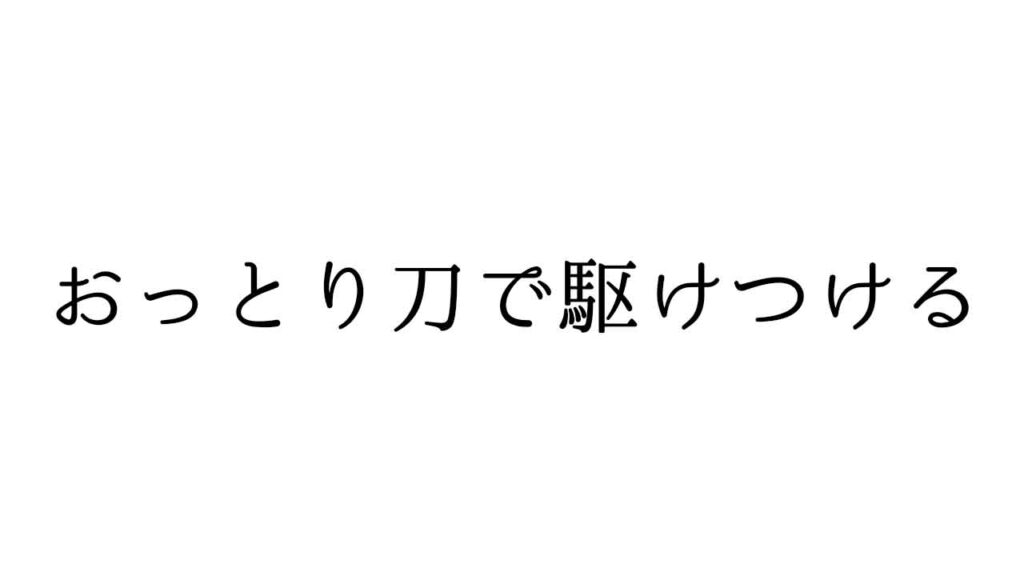「冬山で遭難した人が、服を脱いでいた」というニュースに、首をかしげたことはありませんか。
それは 矛盾脱衣(むじゅんだつい / Paradoxical Undressing) と呼ばれる、重度の低体温症で起こりうる危険なサインです。寒さで生命の危機にあるはずなのに、本人は「暑い」と錯覚して衣服を脱いでしまう――ここに人の生理と脳機能の“逆転”が潜んでいます。
結論:矛盾脱衣は“赤信号”。見かけたら保温・救急・動かしすぎない
矛盾脱衣は、体温が深く低下した末期像のひとつです。衣服を戻して保温し、風雪を避け、救急要請――この3点が最優先。無理な歩行や急速な再加温はリスクになります。
なぜ「寒いのに脱ぐ」のか(メカニズム)
- 末梢血管の“反跳的”拡張
- 低体温の初期は、体は熱を守るために末梢血管を収縮させます。
- しかし進行すると自律神経の制御が破綻し、血管が一気に拡張。皮膚表面に暖かさが一瞬戻ったように感じ、脳が“暑い”と誤認します。
- 脳機能(前頭葉・視床下部)の低下
- 判断力・抑制機能が鈍り、合理的な行動を選べなくなる段階です。
- 「脱いだら危険」という認識が保てず、本能的な錯覚に従って脱衣してしまいます。
- “ショック脱衣”との違い
- 熱中症などで服をゆるめる“ショック脱衣”は、意識明瞭で合理性があります。
- 矛盾脱衣は意識混濁・錯誤下の脱衣で、周囲の状況にそぐわないのが特徴です。
低体温症の進行と主な症状(目安)
- 軽度(35〜32℃):強いふるえ・動作緩慢・うまく話せない
- 中等度(32〜28℃):ふるえが止まる・失調・錯乱・幻覚
- 重度(28℃未満):矛盾脱衣・“潜水行動”(地面にもぐろうとする)・意識消失・致死的不整脈
現場での対応手順(安全最優先)
- 場所の安全確保
- 雪面・風下・落石・雷の危険を避け、できる範囲で防風地点へ移す
- 保温(Wet→Dry→Warm)
- 濡れた衣類があれば可能な範囲で外し、乾いた層で包む(ダウン・毛布・ビビィ・ツェルト)
- 衣服を戻す・体表の熱損失を遮断
- 露出部を覆い、首・腋・鼠径部などからの放熱を防ぐ
- 穏やかな加温
- 使い捨てカイロ等は直接皮膚に貼らず、布越しに体幹部へ
- 飲食は“意識清明・嘔吐なし”が条件
- 可能なら温かい糖質飲料を少量ずつ。意識障害・嘔気があれば経口は避ける
- 観察と体位
- 呼吸・脈拍を継続観察。粗暴な搬送や激しい体動は避ける(致死的不整脈の誘発リスク)
- 通報・連絡
- 位置情報を共有し救急要請。複数人なら役割分担(保温・通報・見張り)
予防:矛盾脱衣の“入口”に立たないために
- 発汗管理とレイヤリング:速乾ベース+保温ミッド+防風アウター。停止前に一枚着る習慣を
- 燃料切れを防ぐ:糖と脂質をこまめに補給。冷たさで手が止まる前に食べる
- アルコールは厳禁:血管拡張で熱を失いやすく、判断力も落ちます
- 単独行動は避け相互チェック:歩行スピード低下・言語のもつれは“初期サイン”
- 気象・雷対策の事前学習:寒冷ストレスの主因は“風・濡れ・天気急変”。出発前に要チェック。
山の天気が急変しやすい理由と予測のコツ
登山中に雷が鳴った時の対処法
冬はなぜ寒いのか?季節の気温を決める仕組み
よくある誤解の整理
- 「寒すぎて服を脱ぎたくなることもある」→ 錯覚と脳機能低下の合わせ技。体は実際には危機的に冷えています
- 「ふるえが止まったから回復」→ 逆。ふるえが止まるのは悪化のサイン
- 「強くこすって温める」→ 末梢循環が急変し、心臓へ負担。優しく・体幹中心に保温を
まとめ
- 矛盾脱衣は重度低体温の赤信号。衣服を戻し、保温と救急要請を最優先に
- メカニズムは血管の反跳的拡張+脳機能低下。合理性のない脱衣が起きる
- 予防は発汗管理・栄養・装備・天気読み。リンク先も事前学習に活用を
- 冬山・寒冷環境では、「寒いのに脱ぐ」現象を知って備えることが命を守る最短ルート