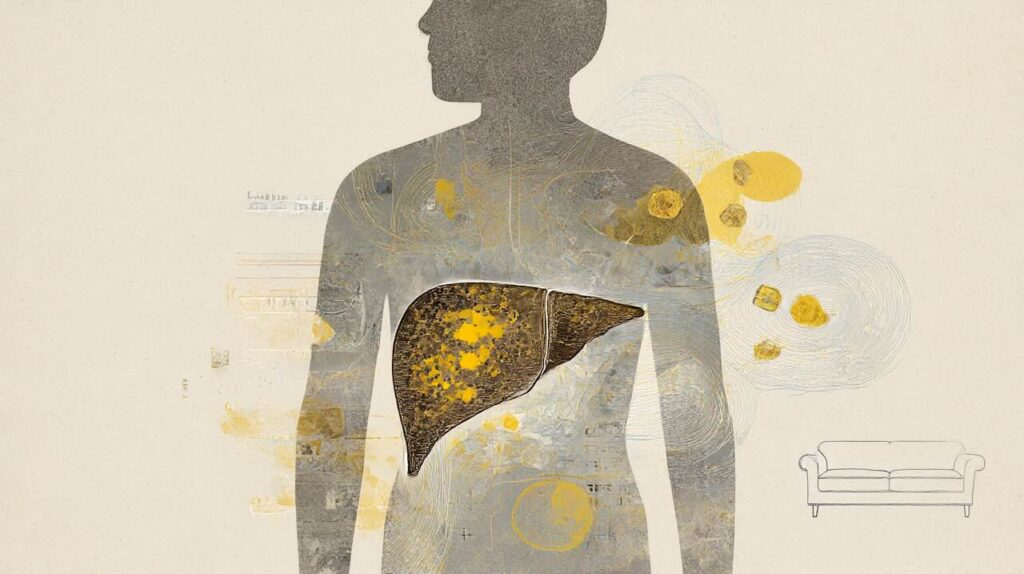「双極性障害って最近よく聞くけど、躁うつ病とどう違うの?」「治る病気なの?」
そんな疑問や不安を持つ方のために、この記事では双極性障害の特徴、原因、治療法、支援のあり方まで、科学的かつやさしく解説します。
双極性障害=躁うつ病?呼び方が変わった理由
双極性障害(Bipolar Disorder)は、以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。今も「双極性感情障害」と表現されることもありますが、医学的には同じ病気を指します。
名前が変わった背景には、「躁うつ病」という表現が誤解を招きやすく、偏見につながること、そして国際的診断基準(DSM・ICD)との整合性を保つ目的がありました。
どんな病気?躁と鬱が交互にやってくる
双極性障害は、極端に気分が高揚する「躁状態」と、深い落ち込みを示す「うつ状態」を繰り返すのが特徴です。
- 躁状態:ハイテンション、睡眠時間が減る、多弁、浪費や無謀な行動
- うつ状態:無気力、自責感、食欲や睡眠の異常、希死念慮(死にたい気持ち)
多くの人が「うつ状態」で受診するため、最初はうつ病と診断されてしまうこともあります。
双極性障害のタイプ:I型とII型がある
- 双極I型:はっきりした躁状態と重度のうつ状態が交互に現れる
- 双極II型:軽い躁状態(軽躁)とうつ状態を繰り返す
タイプごとに治療方針が異なるため、正確な診断がとても重要です。
原因はひとつではない:脳・遺伝・環境の複合要因
双極性障害は「多因子性疾患」とされ、次のような要因が絡み合って発症すると考えられています。
- 遺伝的要因:家族に患者がいるとリスクが高まる
- 脳内の神経伝達物質の乱れ:セロトニンやドーパミンのバランス異常
- ストレスや喪失体験:出産・失恋・失業・人間関係の悪化など
- 生活リズムの乱れ:不規則な睡眠や交代勤務など
これらの要因が重なることで発症・再発のリスクが高まります。
治療法:回復と安定を目指すアプローチ
1. 薬物療法
- 気分安定薬:リチウムやバルプロ酸などが基本
- 抗精神病薬:躁状態の急性期や予防に使われることも
- 抗うつ薬:単独では躁転のリスクがあるため注意が必要
2. 精神療法(心理教育・認知行動療法)
- 自分の症状を理解することで、早期発見と対応が可能に
- 家族と共に病気を学ぶ「家族教育」も回復の鍵
3. 生活リズムの安定
- 規則正しい睡眠と食事、過労を避けた行動パターンが重要
4. 周囲の理解と支援
- 家族・職場・友人の理解が、治療継続と再発予防に大きな意味を持ちます
関連する感情体験とクオリア
双極性障害では、感情の激しい振れ幅が「クオリア(主観的感覚)」と深く結びついています。
詳しくはクオリアとは?意味・特徴・意識との違いをやさしく解説も参考にしてください。
また、情動と神経伝達物質との関係については、「幸せホルモン」セロトニンが睡眠の質を左右するで詳しく紹介しています。
よくある誤解:甘えや性格ではない
「気分の波があるのはわがまま」などと誤解されることもありますが、双極性障害はれっきとした医学的な脳の疾患です。本人の努力や意思だけではコントロールできません。
誤解や偏見をなくすためにも、正しい知識と理解がとても重要です。
市販薬で気分はよくなる?
感情的な痛みについて「ロキソニンのような薬で楽になる」と話題になることもあります。これに関しては、心の傷にもロキソニンが効くって本当?その仕組みと科学的根拠をやさしく解説で詳しく検証しています。
科学的な観点と患者の体験の両面から理解することが大切です。
まとめ
- 双極性障害は「躁うつ病」と同じ病気で、感情の波を繰り返す
- 遺伝・神経伝達物質・生活リズム・ストレスなど複合的要因が関係
- 治療には薬・心理療法・生活支援が重要
- 誤解をなくし、正しい理解が回復と安定の支えになる
病気と向き合うには時間がかかることもありますが、確かな知識と周囲の支援があれば、安定した日常を送ることは十分に可能です。
双極性障害 ――躁うつ病への対処と治療 (ちくま新書)
Amazonで見る