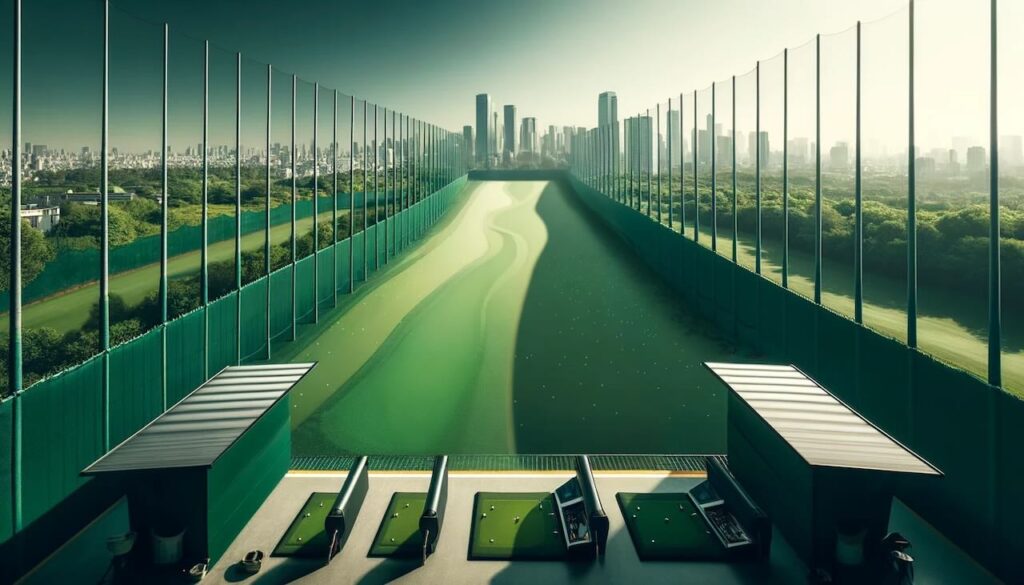ボクシングを観ていると、選手が「赤コーナー」「青コーナー」に分かれて登場しますよね。
なんとなく「赤が王者、青が挑戦者」なんて印象を持っている方も多いかもしれませんが、実際に意味はあるのでしょうか?
この記事では、ボクシングにおける赤コーナーと青コーナーの意味・由来・心理効果までを初心者にもわかりやすく解説します。
赤コーナーと青コーナーの違いとは?
ボクシングでは、試合の演出として選手が「赤コーナー」「青コーナー」に割り振られます。
これは公式ルールではなく、主催者や興行サイドの裁量によって決まります。
| コーナー | 割り当てられやすい選手の傾向 |
|---|---|
| 赤 | チャンピオン、有力選手、地元出身のスターなど |
| 青 | 挑戦者、ビジター、アンダードッグ的存在など |
ただし、これはあくまで傾向に過ぎず、例外も多い点には注意が必要です。
なぜ赤と青が使われるのか?
1. 視認性が非常に高い補色関係
赤と青は、色相環の中でも正反対の位置にある「補色」の関係にあります。
観客、審判、テレビ視聴者が瞬時に選手を判別しやすいという利点があるのです。
実際、曇り・室内でも日焼けする?見落としがちな紫外線リスクと徹底UV対策でも扱っているように、色の識別や可視性は環境や照明の影響を大きく受けるため、視認性の高い色が選ばれるのは理にかなっています。
2. 色の持つ心理的イメージが対照的
- 赤:情熱、攻撃性、力強さ、リーダーシップ
- 青:冷静、安定、理性、防御
このように真逆の印象を持つ色を使うことで、試合の“対決構造”がより際立ち、視覚的にも心理的にもドラマ性が増すのです。
この心理的効果については、心の傷にもロキソニンが効くって本当?その仕組みと科学的根拠をやさしく解説のように、「身体と感情のつながり」が注目される場面でも活かされています。
配色の由来と歴史的背景
赤と青の配色が定着したのは、1920年代の白黒テレビ放送が始まった頃だとされています。
- 白黒映像では明暗が強く出る色が必要
- 赤と青は明るさの差があり、判別しやすかった
また、1936年のベルリンオリンピックでは、ドイツの代表色である赤をホーム選手が使用し、対戦国が青を使ったことも影響したと言われています。
ただし、こうした由来は諸説あり、視認性・演出効果・国際的慣習が複合的に絡み合った結果と見るのが自然です。
他のスポーツにもある「赤と青」の使い分け
赤と青はボクシングに限らず、他の競技でも使われています。
| スポーツ | 使用例 |
|---|---|
| レスリング | 赤と青のシングレット(ユニフォーム) |
| テコンドー | 赤と青の防具 |
| 柔道(国際大会) | 白と青の道着(視認性のため) |
| 柔道(日本国内) | 紅白の帯 |
このように、「視認しやすさ」「公平性」「演出効果」を重視する競技では、赤と青(あるいは白と青)の配色が採用される傾向にあります。
まとめ
- 赤コーナーと青コーナーの割り当てに厳密なルールはなく、主催者判断による演出
- 一般的に赤は王者や主役、青は挑戦者として使われやすい
- 色は視認性が高く、心理的イメージも対照的であることが採用理由
- 白黒テレビ時代やオリンピックなどが背景にあるとされる
- 他の格闘技や競技でも赤と青(または白と青)は定番
赤と青、それぞれの色に込められた意味を知ることで、ボクシング観戦がより奥深く、楽しくなるはずです。
次の試合では、選手がどのコーナーに立つのかにもぜひ注目してみてください。