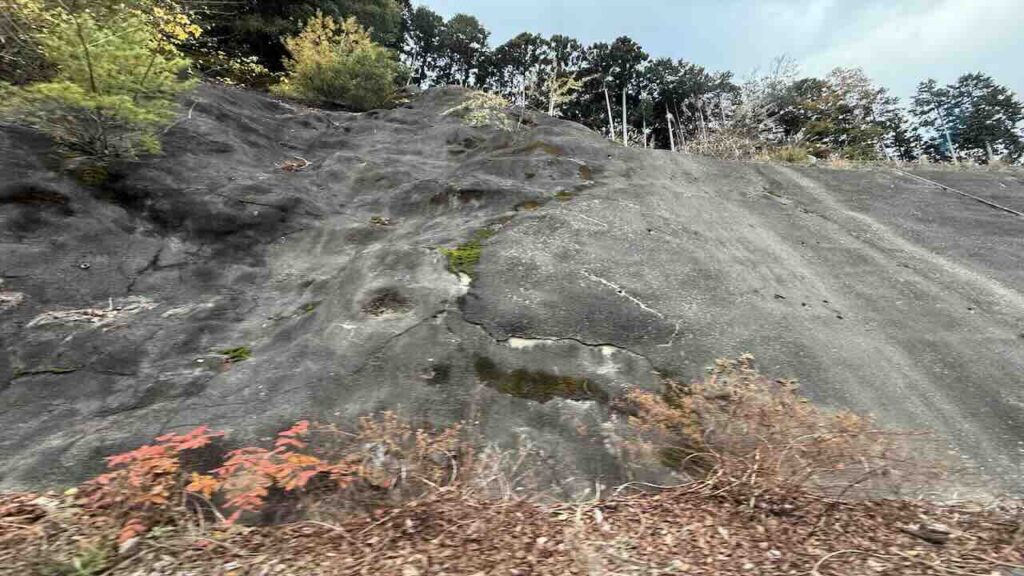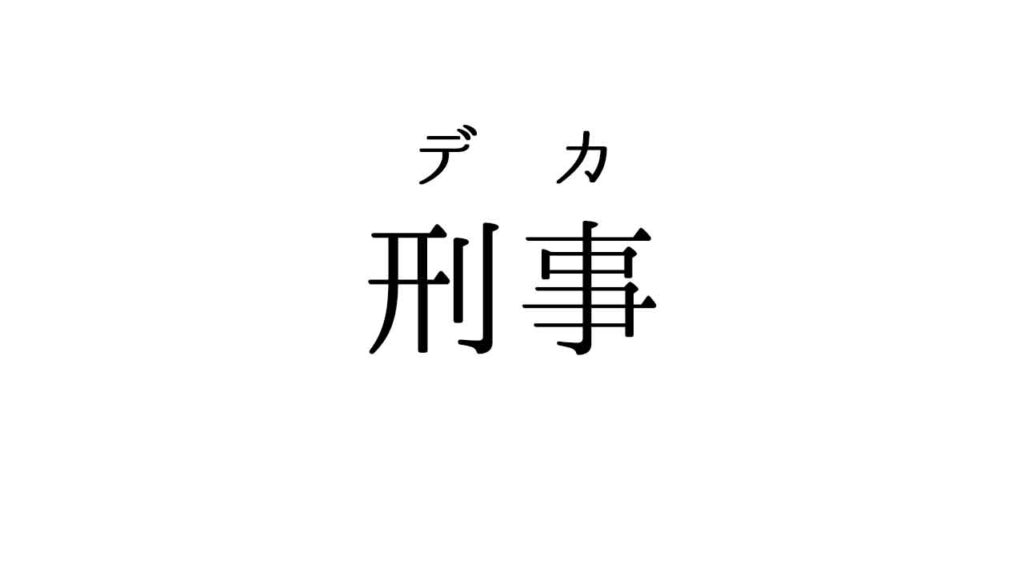「マル暴(まるぼう)」という言葉、刑事ドラマや映画などでよく耳にするけれど、実際にはどんな意味があるの?と感じたことはありませんか?
「暴力団対策に関わる部署の略称」というのは聞いたことがあっても、なぜ「マル」がつくのか、その背景までは意外と知られていません。今回は、そんな「マル暴」の意味・由来・役割について、わかりやすく解説します。
結論:マル暴とは「○暴=暴力団対策部門」の略称
「マル暴」とは、警察組織の中で暴力団対策を専門に担当する部署の俗称です。正式には「暴力団対策課」「組織犯罪対策課」などの名称で、各都道府県警察の刑事部に設置されています。
この「マル」という表現は、警察内部の文書で「○」を使って部署を略記する習慣に由来し、「○暴(まるぼう)」がそのまま「マル暴」と呼ばれるようになったのです。
マル暴の主な仕事とは?
マル暴が担う任務は多岐にわたります。一般的な刑事と異なり、暴力団という組織的な犯罪に対して、長期的・継続的に対処する専門部門です。
1. 暴力団の摘発と取り締まり
- 組員による恐喝・脅迫・賭博などの摘発
- 組織犯罪の構造解明と証拠収集
- 関係先の家宅捜索やマネーロンダリング対策
2. 市民社会との連携による排除活動
- 企業・自治体との連携での暴力団排除運動
- 青少年への啓発活動や暴力団加入防止
- 暴力団からの脱退支援
こうした活動のなかでは、補導とは何?逮捕との違いや対応方法をわかりやすく解説!のように、未成年者との関わりも重要な領域です。
なぜ「マル」がつくのか?
警察組織では、部署を略す際に「○暴(マル暴)」「○知(マル知:公安)」のように、頭に「○」をつける表記が用いられてきました。この○は単なる丸印で、特定の意味は持ちません。
こうした符号は、警察文書の中で部門名を省略するためのものでしたが、いつしかそれが口語表現としても使われ、「マル暴」が定着したのです。
マル暴の捜査官に求められる能力
マル暴の担当者(捜査官)は、一般の刑事よりも特殊な状況での対話・対応が求められます。
- 組織犯罪に対する粘り強さ
- 暴力団関係者との接触に耐える精神力
- 関係者や市民との信頼関係を築く力
- 法律・条例への深い理解と慎重な運用
こうした捜査官は、一般的な刑事の特徴について解説した「刑事のことをなぜデカと呼ぶ?」とも比較される存在です。
マル暴の活動例と現代的課題
最近では、暴力団がインターネットを通じて活動したり、半グレと呼ばれる新たな組織との連携を深めたりする中で、マル暴の役割はますます複雑化しています。
- 暴力団によるSNS上の威圧行為
- 暴力団排除条例に基づく居住地・活動制限
- 市民からの通報を基にした早期対応
このように、マル暴は「表には見えにくいけれど、市民生活の安心を支える縁の下の力持ち」ともいえる存在です。
まとめ
「マル暴」とは、「暴力団担当部門」を示す警察内部略語「○暴(まるぼう)」が語源です。単なる略称にとどまらず、暴力団対策の最前線で活躍する警察官たちの象徴とも言える言葉です。
私たちの暮らしの安全は、こうした見えないところで活動する人々に支えられているということも、ぜひ覚えておきたいですね。
マル暴 ~警視庁暴力団担当刑事~(小学館新書)
Amazonで見る