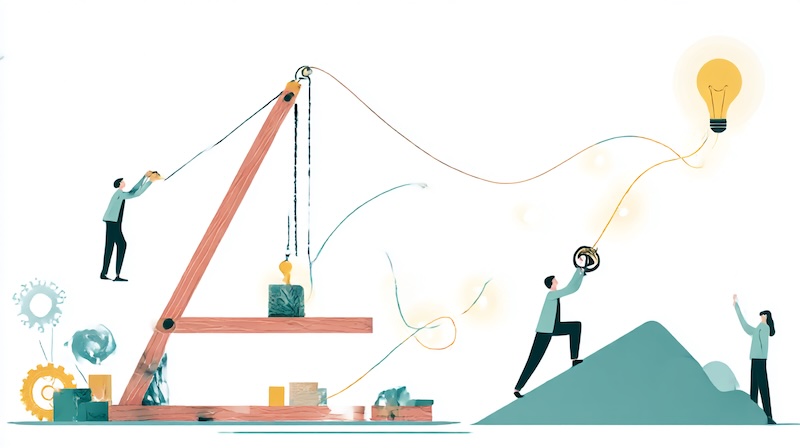「なぜ永遠に動き続ける機械は作れないの?」「スマホの充電ってどうして減るの?」
そんな疑問の答えになるのがエネルギー保存の法則です。高校の授業で聞いたことはあっても、意外と忘れてしまっている人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、エネルギーは消えずに形を変えるだけというのがこの法則。
この考え方を知っていると、身近な現象や機械の仕組みがぐっと分かりやすくなります。
エネルギー保存の法則とは?
エネルギー保存の法則とは、孤立系(外部とのやりとりがない閉じた系)において、エネルギーの総量は常に一定という原理です。
つまりエネルギーはなくなることも、突然生まれることもありません。形を変えて存在し続けます。
この考え方は熱力学第一法則(エネルギーの出入りと内部エネルギーの関係を示す法則)とも深く結びついています。
身近なエネルギーの種類
- 位置エネルギー:高い位置にある物体が持つエネルギー
- 運動エネルギー:動いている物体が持つエネルギー
- 化学エネルギー:燃料や食べ物が持つエネルギー
- 電気エネルギー:電流が持つエネルギー
- 熱エネルギー:温度が高い物体が持つエネルギー
日常で感じられる具体例
1. 落ちるリンゴ
木にぶら下がったリンゴは位置エネルギーを持っています。
落下すると位置エネルギーが運動エネルギーに変わり、地面にぶつかったときには音や熱に変わります。
2. ブランコの揺れ
高く上がったときは位置エネルギーが最大、下りてくるときは運動エネルギーに変化します。
しかししばらくすると止まってしまいます。これは摩擦や空気抵抗でエネルギーが熱や音に変わるためです。
外界とやり取りをしているので、これは「孤立系ではない」例です。
3. 電気ポットでお湯を沸かす
コンセントから得た電気エネルギーが、ポット内で熱エネルギーに変わり、水が温まります。
エネルギーは消えているわけではなく、お湯の温度上昇として残っています。
4. 自動車のエンジン
ガソリンに含まれる化学エネルギーが燃焼により運動エネルギーや熱エネルギーに変わります。
エネルギーは形を変えただけで、失われてはいません。
仕事の原理との違い
よく混同されやすいのが仕事の原理です。
- エネルギー保存の法則:エネルギーは形を変えても全体の量は変わらない
- 仕事の原理:力を小さくすれば、その分動かす距離が長くなる(道具の便利さを生む物理の基本)
仕事の原理については別記事で詳しく解説しています。
詳しくは 仕事の原理とは?道具の便利さを生む物理の基本をご覧ください。
まとめ
- エネルギー保存の法則は「エネルギーは消えず、形を変えて存在し続ける」という自然界の基本ルール
- 成立するのは孤立系であることが前提
- 熱力学第一法則とも深く関連し、日常のさまざまな現象で確認できる
- 仕事の原理はエネルギー保存と関連はあるが、別の視点からの考え方
この法則を知っておくと、身近な疑問も物理的に納得できるようになります。
イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める!物理のしくみ
Amazonで見る